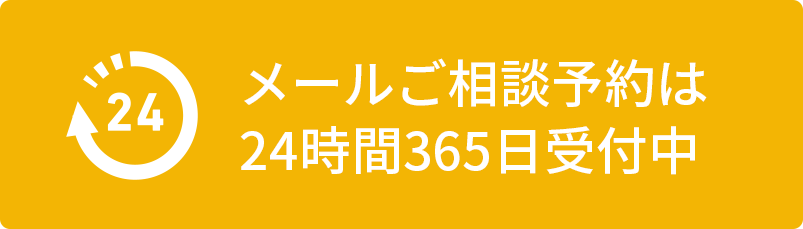面会交流
離婚後の面会交流について、みなさまどのようなお考えをお持ちでしょうか。今回は、離婚後の面会交流について、①弊所での対応を踏まえた裁判所の基本的な考え②実際の審理③この類型の事案の私の対応の指針④よくあるご質問についてをお伝えできればと思います。
①裁判所の基本的な考え
はじめに
裁判所(特に家庭裁判所)は、面会交流について面会することが子にとって不利益を招くような事情がなければ基本的に交流を実現させる方向での進行をさせることが多いです。この点、過去の裁判所の判断で面会交流は、子が非監護親(実際に監護していないという趣旨です)の愛情を感じる重要な機会といった趣旨の表現をしております。
面会交流を阻害する事情
いわゆる虐待であったり、連れ去りの危険であったり等の面会を行うことでの現実的不都合が抽象的危険性でなく、具体的な危険性、過去の行動から実際にその危険があるかといった点から見て頂くと良いと思います。その意味でこの部分を裁判所は「何となくあぶなそう」といった抽象的なもので認定することはおよそありません。
②実際の審理
調停でのお話合い
私のところにご相談に来られる際は、多くの場合、双方での調整がほぼ無理になっている状況です。そうなると、家庭裁判所の調停でお話をすることになります。
ただ、調停は、あくまで裁判所を使った「お話合い」に過ぎませんので気持ちが強固な当事者間での調整は困難を極めます。そうなると上記面会交流の阻害事由の存在も含めて、家庭裁判所調査官による調査がなされます。
家庭裁判所調査官による調査
家庭裁判所調査官は、教育学であったり心理学であったりを専攻している裁判所職員です。
実際の調査は、この方々の知見を踏まえて、当事者双方及び場合によってはお子様からも聴取の上、面会をどうすべきかといった意見を述べることになります。その意見が調査報告書という形で記録化されることになります。
家庭裁判所調査官による調査を踏まえた調停進行
調査を終えると、その調査結果を前提にした進行が多くの場合なされます。また一度の調査後再度の調査はほぼ行われませんので(私も何度か再度の調査をお願いしましたが、なかなか対応してくれる裁判所が少ないのが現状です)、一度の調査で悔いの無いように進めることが大事です。
また、この段階になると調停で合意できなかった場合の審判の見通しを実際に伝えられながらの進行になることも少なくありません。そうなるとこれ以上調停で争って審判に移行するのかといった点も含めて検討する必要があります。
③面会交流類型における弊所の対応指針
私自身も基本的には、裁判所の考えと同様の考えを持っておりますので、面会交流自体、非監護親と子の貴重な交流機会ですので実施されるのが基本的には望ましいと思っております。ただ、その交流が子の成長を阻害するものになってしまうのであれば、どのように実施するのか慎重に考えるべきだと思います。
面会交流についてのよくある質問
養育費との関係
裁判所は、養育費と面会交流について、関連性があるとは考えておりません。個別に一つずつ考えるといった形ですので、それを前提に思って頂ければと思います。
面会交流を強制的に行わせることができるのか
裁判所は、監護親が恣意的な目的で交流を阻害しているといった相当限定的な場合のみですが、一部面会交流の間接強制を認めております(分かりやすくいうと、一度面会交流をしなかったら●万円相手方に支払わないといけないといったようなものです)。ただ、これもかなり限定的な場合の適用ですので、なかなか厳しいのが正直なところです。
面会交流の頻度はどの程度か
実際の事案によって区々というのが正直なところですが、基本的には月に1回前後から開始することが多いです。
親以外との交流
よくある質問であるのが、自分のご両親(子どもから言えば祖父母です)との面会についてです。これについて、まず親との交流とはなりますが、ある程度当事者間の調整が上手くいけば行っている事案も少なくありません。
どれぐらいの期間がかかるか
面会交流は特に感情的な対立が大きくなりやすく半年から1年かかることも少なくありません。
お子様と継続的な交流を目指す為にはその覚悟も必要になってきます。
まとめ
以上見てきたとおり、面会交流もどこから進めていくかどう進めていくかをしっかりと決めないとむやみに時間だけが経過しかねません。どう決めたら良いのかと悩まれている方はお気軽に弊所へご相談ください。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)