財産分与を払わない相手への対処法|調停・裁判の流れと弁護士が解説
離婚離婚後に財産分与を取り決めても、「相手が支払ってくれない」「そもそも応じようとしない」というトラブルは少なくありません。財産分与は法律上の権利であり、支払いを拒否されたからといって諦める必要はありません。
この記事では、財産分与を払わない相手への具体的な対処法を、調停・審判・裁判・強制執行の流れを踏まえて弁護士が解説します。さらに、請求できる期限や実際の解決事例も紹介し、今後の対応に役立つポイントをまとめます。
財産分与は、離婚する際に、親権・養育費・慰謝料(不倫・DV等)・面会交流と同様にしっかりと決めるべきものですので、悔いのない選択をされることをお勧めします。
目次
はじめに
離婚時の「財産分与」は、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分け合う制度です。
しかし、中には「払いたくない」と拒否する相手も少なくありません。本記事では、財産分与を拒む相手に対してどのように対応すべきか、弁護士の視点から解説します。
財産分与とは?基本的な仕組みと対象財産
財産分与の定義と考え方
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(預貯金・不動産・株式等)を2分の1にする制度です。よくある家庭で(あくまで最大公約数的なものとお伝えしているに過ぎません)、夫が主として就労し、妻が家事育児を行うという家計が少なくありません。そういった状況で、夫が就労できているのは、妻の支えがあるからこそであり、婚姻期間中に形成した財産は按分すべきといった考えが根底にあると言われております。
分与の割合はどのように決まるのか
上記のとおり、基本的に2分の1ですが、一方が相当の稼ぎがあった場合であったり、特有財産の混在があり一定程度説明ができている場合は、その点が考慮され、修正されることも少なくありません。
原則としては。2分の1ずつ が目安です。たとえば夫婦共有財産が1,000万円であれば、500万円ずつに分けるのが基本的な考え方となります。もっとも、婚姻期間の長さやそれぞれの貢献度によって修正されることもあります。
財産分与を払わない相手に多い特徴と理由
上記のような法律上の考えが前提ではありますが、典型的に支払いを拒む夫の特徴があります。あくまで私の経験上ですが、参考にして頂けますと幸いです。
自分だけのお金だと述べる夫
よくあるのが専業主婦の支えを何ら考えず、自分だけで稼いだと思っている夫の場合です。自宅で色んな支えがあったからこそ、仕事に集中できたことを考慮しないパターンの方です。
このパターンは理屈の問題ではなく、感情もしくは自分の考えが絶対という人が多いので私の経験上あまり説明しても変わりませんのである程度で見切りをつけて法的手続きを進める方が良いことが多いです。
いわゆるモラハラ夫のパターン
誰のおかげで飯が食えているんだ、お前は楽でいいよなといったことを平然と言うパターンについては、お金を自分のものというより自分が優位にあるはず(ありたい)という方が多い印象です。
このパターンは、意外と理詰めに理解を示すことが少なくありません。ただ、モラハラする方は結構忙しいことも多く時間を取ってゆっくり話せないことも少なくありません。加えて、ある程度専門的な職に就いている方も少なくなく、そのような場合は、弁護士に相談に行くことも少なくない協議で進む場合や相談を前提にかなり勉強し、ある程度の理解をされ、建設的な議論が進むことも少なくありません。
給付することがいやなパターン
とにかく金銭の給付が嫌なバターンです。一切渡すつもりもないような方で話すだけ時間を浪費することになるので、できるだけ早い段階で法的手続きを進めることが良いと思われます。
対応することが嫌なパターン
このパターンも個人的にはどうかと思いますが、裁判手続き自体を拒んで財産分与調停や審判、離婚裁判すら対応しないです。この方は、逆に請求に近い内容になることが多いのでありがたい面が多いのですが、ネックな点としては、財産状況をしっかり調べておく必要があるという点です。
財産分与を払わない相手への対処法
弁護士に相談する
財産分与を求めて、相手方が対応しない以上、ご自身で対応するより弁護士へ依頼の上で交渉した方が経済的メリットの大きい可能性が高いです。あくまで、一定の財産分与給付内容があるという前提ですが、生じる弁護士費用より分与を受ける財産分与の方が大きくなります。
その点の簡単な資産を弁護士への相談で受けることができるので、それを踏まえて依頼を検討しても良いかもしれません。
その後の進行は、弁護士次第ですが、相手方にこのまま拒んだ際の見通しを丁寧に伝えることで相手方が離婚及び財産分与に応じることも少なくないので、そうなると解決までの時間は圧倒的に早くなること、財産分与の面を考えると裁判迄することとそれほど変わらないので、早期のご相談を強くお勧めします。
財産分与調停、財産分与審判、離婚訴訟を利用する
相手方が支払わないと言っている中、支払わせる必要がある以上、上記法的手続きの中で裁判所の判断を受ける外ありません。その上で、ご自身の権利を実現させる必要があります。
財産分与の整理自体、エクセル表を使って各財産の評価を定めることになるのでなかなか慣れていないと難しい手続ではあります。そうなるので、結局、この段階で弁護士に相談・依頼されて進められることが良いのではと個人的には思います。繰り返しになりますが、相手方からの給付という点を考えると、弁護士費用の出費があったとしても依頼するメリットは大きい可能性が高いです。
ここまで法的手続きを行って支払いを相手方が行わないことをそれほど多くはありませんが、そのような場合は強制執行を行うことができますので、それによって、支払を受けることも視野にいれるべきです。
財産分与を支払わない相手方(夫)に対する手続と流れ
協議
なかなかこのような払わないとご自身に対して、述べる方が応じる可能性は高くはないですが、協議で終わると相当短期で解決に繋がりますので、これより良いことはないかと思います。
協議で解決できれば合意書を作成し、全ての解決をしっかり記録することをお勧めします。
ある程度の段階で見切りをつけて、法的手続きを進める必要があります。
調停(離婚調停・財産分与調停)
多くの場合、離婚についても合意できていないことが多いのでおそらく離婚調停を進めることになると思います。ここで離婚の合意ができればいいのですが、それができない場合は、離婚して初めて財産分与ということになるので、あまり話が進展しないです。ただ、裁判官によっては、一度整理してみてはといってくれることもあるのでその場合は進行も望めます。
また、調停を進めて、相手方に申立書が届くと、弁護士に相談を行くことも少なくなく、その場合に相手方が十分な見通しを持った弁護士に相談に行った場合は、流れや見通しを理解することで早期解決に繋がります。もっといい例では、弁護士が就くことも少なくなく、その場合は一気に進行することも多いです。他方で、慣れていない弁護士であれば、いわゆる家庭裁判所で良くとられる考えでない話がされることで期日が長引くことになり、逆に長期化を招くことも少なくありません。
財産分与審判もしくは離婚裁判での解決
財産分与審判もしくは離婚裁判での解決となると、基本的には、裁判所主導の整理になります。そうなると、ある程度法律上の枠組みを前提として整理することになります。調停でも基本的にはそうなのですが、審判や裁判となると調整が出来ないとわかると裁判官が判断することも踏まえて、調整を図っていきます。この前提ですのである程度解決の道筋が経つことになります。相手方に弁護士が就いていないであったり、この種の手続に慣れていない弁護士が相手方であったりすると早めにこの手続に乗せてしまう方が良いのではというのが私の考えです。
この2つの手続の選択としてですが、離婚が成立していれば財産分与審判、そうでなければ離婚裁判を行うということになります。
大きな流れとしては、いわゆる実務慣行に沿った主張反論を行い(基準日時点での財産の整理及びその評価の主張)、双方で争いとなる部分を整理した上で、裁判所の考えを踏まえて、調整を試みた上で、場合によっては当事者から話を聞いて(審判であれば審問・陳述書での整理が多く、裁判であれば尋問という形で行うことが多いです)、その上で判断を行うことになります。
財産分与請求には期間制限があります(法改正有)
現行法では、離婚後2年の除斥期間の適用がありますが、法改正で5年になっております(令和7年9月時点では施行されておりません)。もっとも、時効は別にして早期に進める方が良いかと思いますので、早期解決のために動かれることをお勧めします。
財産分与で損しない為にできること
相手の財産情報をできる限り把握する
弁護士と一緒に進めるとなったとしても、相手方の財産について何も手がかりがないところから探ることは不可能です。例えば、預貯金の情報(銀行名・支店名)であったり証券会社の保有情報であったりを把握することで相手方が財産を開示しなかったとしても手がかりを踏まえて、裁判所を通じた調査手続きでの調査が可能です(調査嘱託手続というものになります)。なお、何ら情報を把握できていない場合に探索的にむやみやたらに調査することを裁判所は認めない傾向にありますのでしっかりと把握することが重要になってきます。
不用意な合意は避ける(特に清算条項を付すことは注意して下さい)
当事者間の合意は基本的に有効となり、それがあればその内容が前提になってしまいます。現実に相手方が財産情報を十分に開示しなかったといった場合においても、清算条項という本件を全て解決するという内容が含まれてしまえば、後から家庭裁判所実務に沿った財産分与を行うことがかなり困難です(場合によっては、終局的な合意とみなさないといった判断を裁判所が行うこともありますが、逆の財産分与が完了しているといった判断をすることも少なくなく、そういった場合は本来受けるはずの分与を受けることができなくなります。
弁護士に相談することをお勧めします
できるだけ早い段階であれば、その段階でやれることといったことの説明を詳細に受けることができます。いろんな弁護士がいるとは思いますが、そのような説明を十分行って頂ける弁護士に相談をして頂き、どう解決するのかのイメージをつかまれることを強くお勧めします。
弁護士へ依頼するメリット
解決への道筋を立てることができる
財産分与手続がどんなものか分からない中ご自身でするとなると、いわば地図を見ずに目的地に向かうようなものかと思います。たまたまたどり着ければいいのですが、より良い方法であったりを見つけることができますので、そこのために依頼するメリットはあるかと思います。ただ、対象財産であったり、分与の可能性を見極めて進めるべきかと思いますので、その点も相談の際に確認されることを強くお勧めします。
手続の見極めを行うことができる
これまで見てきたように、財産分与については、調停で解決するのか審判に移行した方が良いのか、場合によっては裁判を行うべきか、はたまた財産の費消を防ぐために保全手続きが必要であるのかという具合に検討することが少なくありません。ここで言う保全手続きは、一定の担保金を前提に相手方による財産の散逸を防止するために用いられることになります。本件で必要であるかといったことは相談の際に弁護士に確認される方が良いかと思います。
本来保全が必要と思われる事案でこれを行われていない事案があったり、保全が必要でないにかかわらず、これが行われたことから依頼者さんにとって好ましくない結果になったということもありますので、手続の見極めを十分に検討する必要があります。
その段階でのすべきことを行うことができる
特に、財産分与についてとなると、現状のやることをしっかりやっていくことが必要です。例えば、財産の調査を行いうる時なのか、相手方が財産を処分しようとすることから、早々に保全手続きを検討しないといけないのかなどといったところです。
そう言った部分を弁護士と一緒に考え進めるという面で依頼するメリットは大きいと思われます。
よくある質問
Q弁護士に依頼するメリットが高い可能性があるのはどんな時ですか。
婚姻期間が長いときはそう思って頂いていいかと思います。
財産分与をするメリットがある場合は、これを行うこと自体大変な面があるのでご依頼を検討されても良いかと思います。
Q弁護士に依頼する場合としない場合でどれぐらい分与額が変わりますか。
状況によります。
ただ、私の過去の事案では依頼前後で3000万円前後変動があった事案もあります。
Q相談の段階で大体の分与額(取得できる額)を教えてくれますか。
相手方の財産、ご自身の財産をご教示頂ける前提ですが、その上でお話を頂くことができます。
Q保全手続きをした方がいい場合はどういう場合ですか。
例えば、生活の本拠となる自宅の処分がされる可能性が高い時、分与の基礎となる財産が散逸される恐れがある時(例えば、退職金の給付が迫っている時)です。
実際にするとなるとある程度費用も必要になってきますので、そこはしっかり検討されることが必要です。
解決事例
受任前
ご依頼頂いたのは、夫側でした。多くの場合、夫側が給付することが多いのですが、夫婦共働きで夫側の収入で生活をし、妻側の収入を貯金するといった形で財産形成をされている方で、妻側も公務員として就労し、相当収入があるという方でした。
ある程度、早期に進めたいとの前提でしたので、離婚を先行させ、財産分与のみ調停で進めるという形で進行することをお伝えし、その点に納得頂き、ご依頼頂きました。
受任後
相手方へ連絡した際に、相手方にも代理弁護士が就き、離婚を先行することは合意をもらい、当初の予定通り進行することができました。その上で、財産を開示した上での財産分与について、相手方に伝えたところ、相手方本人の意向でなかなか開示を受けることができませんでした。
そのような状況でしたので、財産分与調停を申立てた上で、調査嘱託(裁判所を用いた開示手続の利用)を検討していることを伝えた上で、資料の開示を再度依頼したところ、相手方弁護士が説得してくれたようで、資料の開示を行ってくれました。
その後、財産関係の整理をしたところ1000万円を超えると分与を受けることになりました。
事件を振り返って
本件は、必要な手続をその時その時で考えることが功を奏した事案です。おそらくあのまま協議をやっててもこのような結果にはならなかったと思います。手続の限界を十分理解して、見極めることの重要性を理化した事案でした。それこそ当初は、給付すべきものがないと言われていた中、1000万円を超える分与を受けましたので、ご依頼頂くメリットがあった事案だと実感しております。
多くの場合、妻側が分与を受けるのが多いのは間違いないのですが、本件のように結局夫婦の財産の推移によってどちらが分与を受けるかは変わってきます。安易に分与する方される方と考えるのでなく、弁護士への相談をお勧めします。
まとめ
ここまで見てきたとおり、財産分与は動く金銭をはじめとした財産が大きいわりに手続がかなり複雑です。
どうするのが最適かはご自身の状況によって変わってきます。あなたへのオーダーメイドのご提案ができるかと思いますので弁護士への相談を強くお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
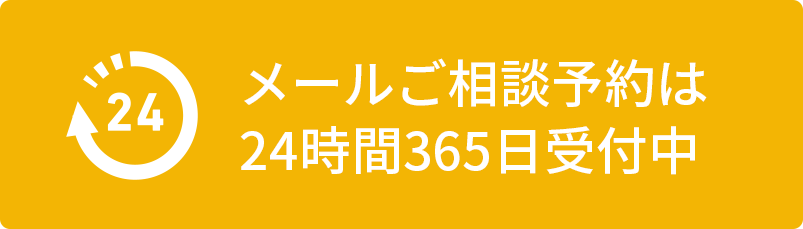

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。