不倫裁判の費用はいくら?誰が負担する?流れと費用を弁護士が解説
慰謝料目次
不倫裁判にかかる主な費用
不倫裁判を起こす・対応する際には、いくつかの費用が発生します。大きく分けると以下の3種類です。
裁判所へ納める収入印紙
分かりやすく言えば、裁判所を利用する費用です。相手方へ請求する金額によって変動しますので、どのような金額を請求するか十分検討する必要があります。なお、令和7年9月時点では、収入印紙を購入して裁判所に納付することになりますが、裁判所のオンライン化の流れで、この購入自体もなくなると言われております。
郵便切手相当の費用
裁判所書類の送達は、原則郵便による方法で行われます。その為、訴えを起こした方が、事前に裁判所へ各裁判所で定められた郵便切手を納める必要があります。もっとも、これまでは郵便切手そのものを納める必要があり、余ったものは裁判所から返却を受けておりました(お客様は多くの場合、こんなに郵便切手を返されても困ると仰ってました)。もっとも、手続の変更があり、少なくとも弁護士が手続を進める上では、多くの場合、わざわざ郵便切手で裁判所に納める必要がなくなり、また余った郵便代相当も現金で返金されることになっております。
弁護士費用
弁護士の私が言うのもなんですが、上記2つは高くとも数万円収まることが多いのですが、この弁護士費用が費用の大半を占めることになります。そこで相手方から回収できる金額もしくは相手方の請求を減額できる金額の目途をつけて弁護士に依頼することとどちらがメリットが大きいかをしっかり選択することが必要です。本件における見通し等を面談の際に弁護士からしっかりと確認されることをお勧めします。
不倫裁判の費用は誰の負担になるのか?(相手方負担は可能か?)
一部であれば可能です。
判決まで言った場合は、弁護士費用相当として、請求金額の1割程度加算した金額が認められることが実務の流れとして多いです。また、裁判所への費用であったり、郵便切手相当の費用については、費用確定の処分を行うことで相手方へ負担をさせることはできます。
現実的には少しでも金額を押さえる方が良いかもしれません。
上記のとおり相手方に費用負担の一部をさせることは可能です。ただ、裁判で判決まで行くことはそれほど多くないこと(裏を返せば和解で終わると弁護士費用の一部を相手方に負担させることはできません)、また、そもそも実際の弁護士費用は、請求額の1割を大きく超えることが多いこと、費用確定の処分によって確定できる金額自体、手間の割にそれほど金額が多くならず、あまり現実的ではありません。そうなると、少しでももとから生じる金額を少なくするかといった視点で最初から考えていくのが現実的かなと思います。
和解で終わった場合は?
相手方に負担させることはできません。
不倫裁判の流れ
協議
訴訟前に協議を行うことがほとんどです。実際これで進展が望めない場合に裁判をすることになるといった印象です。
協議で終わるのであれば、半年以内に解決できることが多いです。
訴えの提起
協議で解決ができなかった場合は、裁判費用を負担して、訴訟を提起することになります。
主張の整理
双方で主張する事実関係について、認否(争うのか前提とするのか)を整理して進めることになります。
なお、この整理が終わった段階を目途に和解(双方での調整の可否)の検討を行うことになります。
人証調べ
主張整理後の和解の調整で解決することが相応にあるのですが、それで解決に至らなかった場合、当事者及び事実関係の確定に必要な人から裁判所で話を聞くことを行うことになります。この段階で不貞行為の内容について、浮気相手・配偶者に話を聞くことが多いです。もっとも、証拠がしっかりあるのであれば、場合によっては、この人証手続をしないことも場合によってはあり得ますが、結局損害部分での法的評価にかかわることが多く、人証調べがなされることが多いです。
判決
和解できない場合は、裁判所が判断を行うことになります。この判決に一方当事者が不服であれば、上級審(控訴審である高等裁判所、上告審である最高裁判所)での審理を受けることになります。
訴訟費用を少しでも抑える方法
訴え提起する裁判所をしっかり検討する
多くの事案で、法律上複数の裁判所で訴訟を行うことができます。これを法律上「管轄」といいますが、いわゆる不倫裁裁判では、請求者側の住所地、相手方住所地、不法行為地である不倫の場所を選ぶことができます。もっとも、複雑な話を言うと相手方が争ってきた場合は裁判を行う場所から争点になります。事案によりますが、あなたの住所の近く、どちらかというと、弁護士と一緒に進められているのであれば、弁護士の移動費用、出張日当の兼ね合いもあるのでそちらに近い方が良いかもしれません。こういった形で費用をしっかりと低く抑える意識を持つことが必要です。
請求する金額をしっかり考える
ここまで述べてきたとおり、裁判所へ納める訴訟提起の手数料は請求金額によって変わります。裁判相場よりかなり大きな金額を請求するのは、この部分の費用が無断になりかねないので十分な注意が必要です。
和解を視野にいれて裁判を進める
判決になる場合は、多くの手続で尋問手続きが行われることになります。この手続自体は、双方及び必要な証人から話を聞くといった手続きです。これ自体、基本的に裁判所で行うということになりますので、移動等の費用が掛かってきます。もっとも、ここまでこじれたのであれば、移動費以上にしっかりとやることをやって判決をしてもらうということも検討すべきかもしれません。
訴訟提起後も初回期日前での解決を目指す
端的に言うと、この場合、裁判所に納める費用が半額程度返ってくる可能性があります。別途手続は必要ですが、それほど煩雑なものではありませんので、そういった意味で本手続を使えるよう、訴訟提起後も相手方が交渉に応じるのであれば試してみてもよいかもしれません。ただ、多くの場合、交渉が上手く行かなかったから訴訟をしていること、納めた収入印紙等の費用の半額となるとそれほど多額になることが少なくないことなどに照らすと、この手続を使う場合は相当限定的かもしれません。
費用の大半は弁護士費用になるが、それでも弁護士に依頼すべきか
請求側で弁護士に依頼しないで進めるのはなかなか困難です
実際ご自身で具体的な請求内容を整理して、まとめて「訴状」を作成する必要があります。この記載方法は独特のルールが少なくなく、相当勉強しないとご自身でこれを作成するのは難しいです。
その他、夫や妻との離婚について今後紛争になることに備えて、どうすることでしっかりと事実認定を取得するかという点や支払われなかった時の対応という点やどう進めるかの安心、その後の対応も含めて依頼するメリットは大きいです。また早期解決に繋がりますので時間的なメリットもあるかと思います。
請求される側でも依頼した方が経済的メリットが大きい場合が多いです
この種の事案ではよほど悪質な事案でもない限り、原告の請求額から相応に減額されることが多いです。そして、弁護士が介入し、すべき反論を行えばその金額も相当大きくなってきます。実際多くの事案で、弁護士費用を考えても依頼した方が経済的メリットの大きくなる可能性が高いです。
実際に依頼しないで進めた方が良い場合もあります
請求側でかなりご自身で調べられてかつそれほど多額の金額を請求することを考えていない場合や被請求額で争う部分はご自身の資力の関係等であったりといった場合は弁護士に頼まず進める余地もあるかと思います。事務所によってはご自身でやるという選択肢も一緒に考えてくれるところもあるかと思いますので、弁護士によく相談されることをお勧めします。
多くの場合、弁護士に依頼することで有利になるのですが、そうとも言えない場合もあり、そこは法律相談で確認されることをお勧めします。
よくある質問
弁護士費用は事務所によって異なるのか
異なります。
かつては、統一した報酬基準が用いられておりましたが、現在は自由化されており、事務所によって区々です。
もっとも、多くの場合、地域である程度の枠内に収まっていることが多いです。費用も含めて、弁護士に依頼されるのであれば、どの事務所が良いかを検討されることをお勧めします。
裁判所へ納める費用は裁判所によって変わるのか
変わる部分と変わらない部分があります。
裁判費用そのものは(収入印紙で治めるものです)、全国一律ですので、変動はありません。
他方で、郵便切手相当の前納分は各裁判所で定められておりますので、少しずつ変わってきます。ただ、多少金額が変わる程度と思って頂ければと思います。もっとも、前納分が少し変わるにしても余った部分は返還してくれますので、文字どおり使った部分ですので、それほど気にしなくてもよいかもしれません。
解決事例
受任前
いわゆる不倫に対する請求でご依頼頂きました。相手方の住所分かるが対応するが不明といったものでした。
受任後
ご契約後、相手方へ書面を送付したところ、一定額の提示がありましたが、同種の事案とは乖離した数十万円の提示というもので、全く対応しうるものではありませんでした。証拠関係もしっかりしており、いわゆる男女の関係であると分かるような一定時間の個室での滞在の証拠もある状況でした。
そこで、訴訟提起した旨及び最終案として、一定額の支払いがあれば、訴訟は取り下げるとの話を伝えました。そうしたところ速やかな支払いがあり(金額としては不貞慰謝料で十分相場の範囲と呼べるものでした)、取下げを行いました。そして、初回期日前に取り下げたことで、裁判所より訴訟費用の半額相当の返金がありました。
解決にあたって
本件は、訴訟提起後、第1回期日前に相手方が支払ってきたというものという珍しいものですが、粘り強く交渉を続けた結果です。相手方も弁護士を就けなかったことから裁判に強い抵抗を示し、このような解決に繋がったと思われますが、こういった解決もあり得ます。初回期日前であれば、一部訴訟費用は返還されることになりますので(ただ、それほどの金額という訳でもありませんし、裁判所によって時期に差があります)、こういった解決もあると念頭に置いて頂いてもよいかもしれません。
不倫裁判の具体的な流れや注意点については、
まとめ
訴訟費用について、様々な規律があり場合によっては相手方に負担させることもできますが、それ自体も知っているか知らないかに依存します。
一度相談することで、より良い解決の方法が見つかると思いますので、お気軽に弁護士への相談をお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
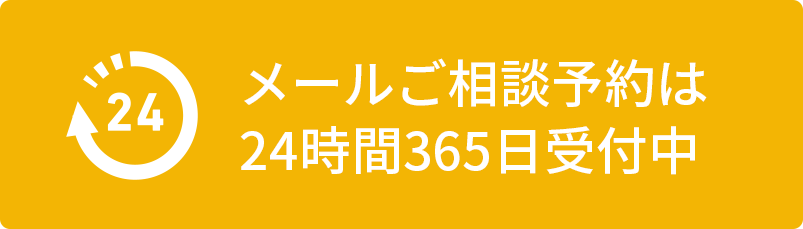

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。