離婚に理由は必要?協議・調停・裁判の違いと弁護士が解説
離婚目次
離婚に理由は本当に必要?
協議離婚では理由なしでもOK
基本的に何かしら理由があって離婚したいという結論になったのだとは思いますが、双方合意があれば、明確な理由がなくとも離婚は可能です。私人間の関係を規律する民法は、私的自治の原則(当事者間での合意が尊重させるというものです)を取っており、よほど不当なものでもない限り、その内容が尊重されます。
調停や裁判で理由が必要になるケース
離婚の上での手続きは、協議、離婚調停、離婚裁判と続いていくのですが、協議・離婚調停の手続は最終的に、双方合意を目指すことになります。その意味から相手方からの合意をもらえない場合は、結局裁判官から、「離婚する」という判決をもらう必要があります。その意味で裁判官に離婚を認めるための「要件」を備えているかが重要になってきます。
離婚を効率よく進めるには
以上のように離婚について、合意をもらえるか、これがもらえないのであれば法律上の要件如何になってきます。ですので、その要件を満たしているのかを確認しつつ、どの段階で手続きを進めるのかを確認しながら見通しをもって進めていくべきです。
配偶者が離婚に合意してくれない中、離婚するには?
離婚に向けての流れ
まず協議
弁護士によって進め方も違いますが、多く場合任意に合意してくれる可能性もあるので、協議から進めることが多いかなというのが私の印象です。当事者同士ではうまくいかなかった協議での解決も弁護士が介入することでご自身の本気度を伝えることができること、弁護士が相手方と交渉することで裁判になった際の見通しを伝えながら交渉できること(結論がこうなる可能性が高いので早い段階でその内容で終わる方が良いのではといった方向で話することが少なくありません)、弁護士が就いたことで相手方も弁護士に相談に行きその関係で実際の見通しについて実感を持って理解することから協議の合意に繋がることも少なくありません。
ですので、いきなり離婚調停という弁護士も少なくありませんが、協議で調整することを試みるメリットはあるのではと個人的には考えております。
協議での解決が厳しければ調停
調停は裁判所を使った話し合いです。法律上離婚訴訟の前に調停を行うことが要請されている調停前置がなされていることから離婚訴訟を行う前提として調停を行う必要があります。この調停は、調停委員を間に入れた上で、双方の考えを確認して、柔軟な合意形成を図るというものです。この後の離婚訴訟になると、ある程度法律論を前提とした解決になることから、夫婦間の問題を柔軟に解決するものとして用意されている制度です。
協議で解決しなかったのに解決するのかという風にみなさま疑問に思われるかもしれませんが、調停での解決が少なくなく、私の経験上当事者のみなさまのお気持ちの点もあってか訴訟までいくのはよほどの事案といった印象を持っております。少なくとも双方に代理人が就いている中で訴訟まで行くのはかなり主張が対立しているか、ご本人の意向が強いかといったのいずれかのことが多いです。また、調停で決まった内容については、強制執行も可能であることから双方でしっかりとした取り決めを行うという趣旨でかかる方法で何とか相手方の合意を勝ち取るということも少なくありません。
調停での解決ができなければ離婚裁判
繰り返しになりますが、ここまでくるものの数は相対的に多いわけではありません。ただ、ここまでくると、法律上の要件を満たすかという点を前提に、その上で、当事者での調整を図ることが少なくないです。みなさまも裁判になったとしても和解での解決がほとんどであるということを聞くことも少なくないと思いますが、そのこと自体は紛れもなく事実です。とはいえ、調停等と同じような進行では決してくなく、法律上の整理を前提に進んでいくことになります。その進行で整理した中で、双方が合意できうる内容を裁判所が模索することになります。このような前提ですので、ある程度実務慣行に沿った整理が必要になります。
以上のとおり、協議・調停・裁判といった順序で形式的な要件を満たす事項が多くなり、手続が複雑になってくるということになります。そして、相手方が応じてくれない限り、順番に進めていくということになります。
民法770条で認められる離婚原因
不貞行為である浮気・不倫(民法770条1項1号)
いわゆる浮気(不倫)で配偶者が他の異性との性交渉があったかです。この法律で問題なるのはいわゆる性交渉でそれがあったか否かという点が重要な判断要素になってきます。もっと言うと、性交渉を推認しうる事実認定がなされるか否かが重要な要素になってきます。具体例として考えられるものは、一定時間における2人での密室での滞在、性交渉を前提とするやり取りです。夫・妻に浮気されたとして、様々な証拠や事実関係をご教示頂くことが少なくないですが、決定的なものとしては、上記事実関係で、その他のものは金額を定める上での考慮要素になってくる可能性が高いのかなというのが私の印象です。不貞行為である浮気は、法律上、離婚要件とされているのですが、その他の一切の事情を加味して、請求を認めないことも可能であるとされており(民法770条2項をご参照下さい)、相手方の浮気がどれほどひどいものであり、それによって夫婦関係が修復不可能であることをしっかりと主張することが重要です。
また、不貞行為や浮気については、特定(相手方、日時、場所、どれぐらいの頻度、何をしたのか)及びそれに基づく証拠を整理した上で、裁判官の判断に耐えうる整理が必要になります。なお、本要件を満たす場合は、慰謝料の請求も可能ですので、しっかりとその点の整理も併せてすることが必要です。
悪意の遺棄(民法770条1項2号)
本条の定める離婚要件は、いわゆる「悪意の遺棄」と定義されるものです。一般に、社会倫理的に非難に値する正当な理由のない同居・協力義務の放棄とされています。一般的には、要扶養状態にあるにもかかわらず、何らの扶助をしないことと言われております。
悪意の遺棄が、他方当事者から主張されることも少なくありませんが、過去の裁判例で「悪意の遺棄」を認めたリーディングケースとしているのは、女性問題がありかつ相当の暴力を行っており生活費も支払わないという事案で認めている程度で、裁判所がこれを踏まえて同主張を認定しているものは多くありません。法律上の要件として、存在しますが、本要件を満たすことから離婚成立というのはなかなか困難というのが正直なところです。
3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
3年以上の生死不明となると、本要件が当てはまりますが、相手方が離婚請求、もっと言うと離婚訴訟に対応しないとなるとその事実も考慮して、判断をすることが少なくありません。言うなれば、対応しないことから反論する意思がないとして進行することが多いと考えて頂いて問題ないです。担当の裁判所次第の面はありますが、不出頭の事実を踏まえて、離婚自体に争わないとされることが少なくないので、3年まで待つ必要がないのかなというのが私の正直な感想です。法律上、家事事件については、不出頭であるかといって他方当事者の主張を前提にするという訳ではありませんが、その事実自体は考慮されるということになります。
強度の精神病(民法770条1項4号)
この要件についても、回復の見込みがないという要件に対する主張がなかなか困難なこともあり、本要件に該当することを前提に離婚を求めることはあまり多くないのが現状かなというのが私の肌感です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)
はじめに
離婚請求をする際には、ほぼ間違いなくといってよいぐらい本要件の該当性を前提に主張することになります。というのも、本要件は、かなり評価的な要素が強く、夫婦間の紛争自体を本要件に該当されることが可能であるからです。
もっとも、本要件の該当性として、よく用いられるものは、主として、不貞とまで言えない異性関係、一定期間の別居、離婚意思の一致、その他の事由といったところが挙げられます。以下ではその辺りを簡単に概観します。
不貞とまで言えない異性関係
性交渉までは推認できないにせよ、性交渉類似行為もしくは他方配偶者を裏切るような行為でこの辺りが主張されることが多いです。この主張をするにしても具体的事実の特定が必要であること、本要件自体がかなり評価的側面を含むものですので、程度として「悪い」ものであることを強調できる程度に主張することが必要です。
これだけというより、他の本条文の要件と併せて主張することが多いです(このことは、離婚事由一般に言えますが…)。
一定期間の別居
離婚事由全体を含めて、一番使うことが多いのが本要件であると言っても言われるぐらい離婚主張する際には使われるぐらいのものです。この別居は過去の裁判例で、民法770条1項5号の解釈とされており、特に、重要なメルクマールとされております。この期間について、判断する裁判官によるというのが大前提ではありますが、過去の裁判例を踏まえると、婚姻時の同居期間と同程度もしくは3年を超える程度のいずれか短い方といったイメージです。もっとも、未成熟子の存在等で事情が変わってきますので、その点については面談の際に弁護士に確認されることを強くお勧めします。何となく、長期間で押さえられている方もいらっしゃると思いますが、現実には、上記期間程度で整理されることがほとんどです。なお、現在の日本の裁判所の判断の傾向としてですが、特段一方が一方的に悪いという事情があった場合は(一方による不貞行為などがその代表例と言われております)、別居期間について、およそ7年程度と言われております。この別居期間についても、あくまで目安に過ぎず、この期間のみに着目して、不誠実な態度で離婚要求した場合は、そのことをもって離婚を認めないとした裁判例も存在しますので、ご注意ください。
相手によるDV(暴力)
上記別居と共に、よく離婚事由として、主張し、裁判所が場合によって人しているのが、暴力でよくDVといわれるものです。これについては、民法770条1項5号の適用の代表的なものといってよいものかと思います。その上で、不貞行為と同様に損害賠償請求の対象になります。
離婚事由の認定の上では、相応のDV(暴力)の事実認定が取れれば良いのですが(一般に録音・録画、警察の聴取記録、診断書等が状況によって必要です)、結局損害賠償請求を行うことが多いですので、暴行によってどういう損害が生じたのかというのを従前の収入状況やけがの状況を踏まえて主張することになります。
DVを理由に離婚を請求する場合は、早期の段階で上記資料の準備を行うことをお勧めします。
離婚意思の一致
条件面はともかく、離婚意思に争いがない場合、そのことをもって婚姻を継続し難い事由としている裁判例も少なくありません。双方から離婚を求める裁判がされていた事案で、そのことをもっても離婚意思が一致しているとしておりました。確かに、双方が離婚を求めている状況では修復することもないので、その上で、婚姻を継続し難いという評価になるのは妥当であると感じたのは私自身印象に残っております。
その他の事由
この辺りについて、みなさまがお考えになるのはモラハラや金銭的DVといったものかと思います。もっとも、この辺りは最近出てきたものであることから、裁判例でこれだけで離婚を認めたものは正直なところそれほど多くはありません。裁判例で認められている代表的なものとしては、他方配偶者が過度に宗教に傾倒しているであったり、義理の両親との不仲でかつ他方配偶者がその点について調整をしないであったりといったものです。このような事情が存在すれば、この部分で認めてくれる可能性も少なくありませんので、しっかりと弁護士に確認されて下さい。
配偶者が離婚に応じない場合の対処法
弁護士に相談するメリット
配偶者との離婚を考えた段階でまず弁護士に相談をすることをお勧めします。その上で、ご相談した弁護士にどうすれば早く離婚できるか、どう進めるべきかと確認されることをお勧めします。その上で、ご自身で進めることができるかを考えて頂いて、依頼も含めて検討されることをお勧めします。相談で方針を確認した上で、弁護士へ依頼することで配偶者へ離婚に対しての本気度も伝わりますし、進行のイメージを持つことができると思います。
そういう意味で、弁護士への相談・依頼を離婚に応じてくれない配偶者と離婚する方法のまず一歩と考えてもよいかもしれません。
相手方への条件提示(財産・子ども・慰謝料を含めた条件整理)
離婚するに際しては、条件面の調整が必要です。弁護士と行うか否かはともかく、結局何らかの条件で離婚を進めることになります。条件面をどのように調整するかはともかく、早期に離婚を進めるのであれば、終局的なものであるかはともかくとして条件提示をしていくことが必要です。この条件は、一般論として、一度出すとそれより有利な条件を事後的に出すことはなかなか厳しいですのでその点は慎重になられるべきです。
よくあるものとしては、離婚する上で支払うお金、財産分与の調整、自宅である持ち家をどちらが取得するかといったものです。その他、お子さんがいらっしゃるのであれば、親権・養育費・面会交流も調整の対象になってきます。どのような条件であれば提示するかといった点を弁護士と相談するもしくはご自身で考えられるのであれば十分検討の上、すべきです。
調停の申立てと流れ
条件を提示しても対応がない、条件面で隔たりが大きいということも少なくありません。その場合は、家庭裁判所への離婚調停の申立て(裁判所上の名称は夫婦関係調整調停(離婚という名称になっております)を早々に検討すべきです。対応しないまま待つとどこまでいっても時間が経つだけです。また条件面で隔たりが大きいと、それ以上協議を進めても解決の糸口は見つけられないと思います。であれば、調停を早々に申し立てるべきということになります。そうした結果、例えば、夫もしくは妻が裁判になって長期化かつ弁護士が必要であれば早期に調整すること、調停委員会案が出ることも少なくなくそれに呼応して解決ということも実際にはままある状況です。
調停を申し立てて、そこでの解決ができなかったとしても、離婚裁判で解決する際に、日本の法制度上、調停前置が取られていますので、調停をしておく必要が無駄にはなりませんので、その意味で離婚調停をしておくのは重要な手続です。
早期に離婚を応じてくれないケース(比較的多いケースです)
夫に経済的に依存している妻への離婚請求
離婚すると夫婦の協力扶助義務がなくなり、自分で就労し生活しないといけないことから離婚を拒むケースです。この場合は、婚姻関係を破綻していることは認識しつつ、生活の為・金銭給付のために離婚を拒んでいるパターンです。
私がお勧めすることが多い方法としては、上記条件提示・法的手段を進めることになりますが、その過程の中で離婚事由をどの程度満たしているのか(例えば、ある程度別居期間があるのかなど)といったところを見ながら条件を見極めて進めていくことが多く、結果として、早期解決に繋がることが多いです。
妻に対して愛情があると訴え続ける夫への離婚請求
この場合は、今後の見通しであったりを踏まえた判断ということはあまり想定できず、結局妻側に復縁の意思がないことを明示して、分かってもらうことが一番大事なのかというのが私の印象です。調停や裁判でどうなるかを伝えて、なお裁判所からも伝えてもらって進めることが良いのではというのが私の感覚です。ただ、そのように代理人、裁判所から伝えても納得することが少なく、最終的に裁判所に判決という形で進めることが多いのではというのが私のこれまでの経験上の形です。
何ら対応がない配偶者への離婚請求
この場合も、ある程度時間が掛かるという分類しておりますが、本記事でご説明したとおり、裁判さえすれば、請求が認められる可能性が高いです。そうなると、裁判までいかに早く進めるかということになりますので、その辺りも踏まえて調停進行することが大事かなというのが私の経験上のお伝えということになります。
離婚を進めるに際して、特に難航長期化してしまうケース
ご自身が不貞行為・浮気等の有責に該当する行為をしてしまっている場合
これは、前述したとおりですが、蓄積した裁判例で、浮気したものからの離婚請求については、別居後相当期間離婚を認めないとしており、概ね7年程度別居することを前提に子どもの状況等を踏まえて判断することになっております。そうすると、裁判所に判断を仰げば離婚が認められにくいという状況で、離婚するためにどう進めるかが必要になります。そこで条件面の調整が必要になってきますので、離婚することが難航します。重ねてですが、有責性として、暴力であったりもこの点に密接に絡むことも少なくありません。
自宅の取得を双方が主張している場合
この部分で争いがあると、調整が厳しくなってしまうことも少なくありません。双方が取得を主張し譲らなかった場合、判決まで行く可能性もありそして結果に納得しない方は、控訴することもありえ、その意味で長期化しかねません。その他本件と関連してですが、主張の対立が激しい場合は、控訴審迄及ぶ可能性が少なくなく、そうなると長期化しかねません。
よくある質問
相手方が離婚に拒んでいる場合どれぐらい期間がかかるか
この点については、ケースバイケースと言わざるを得ません。
ただ、それのみで終わってしまうと回答になっていないと思いますので、多くの場合という意味でご回答差し上げます。相手方がどこかの時点で離婚を前提に話し合いの折り合いがついた場合に限れば、争点が少なければ2年を見ていれば終わるケースが多いです。手続毎のイメージをお伝えすると、協議で終われるのであれば半年から1年程度、調停であれば半年から1年半程度、裁判であれば1年から2年程度といったものです。これについては相手方にも弁護士が就いて財産整理がスムーズにいった場合を前提にしておりますので、財産に関する調整が上手く行かなかった場合(進行に時間を要した場合)等はもう少しかかるといったイメージを持って頂けますと幸いです。
他方で、相手方が折り合いをつけることなく、判決・控訴審・場合によっては上告審になる場合、2年以上、もう少しかかる可能性もあるといったイメージを持って頂けますと幸いです。
相手方が離婚を拒むことで弁護士費用は変わるのか
相手方が離婚を拒むからというより、拒まれることで次の手続に移行することによって追加で費用が掛かる可能性が高いと思われます。
現状弁護士費用は、自由化され各事務所によって異なりますが、同類型の事案でかつ近い地域であれば似たような料金設定の可能性が高いです。そして、離婚分野では、上記のように手続移行毎に費用が発生しているところが多いといった印象です。
費用の点は、依頼する上で特に重要な点かと思いますので、しっかり確認されることをお勧めします。
相手方が離婚を拒む理由はどんなものが多いですか
特に拒んでいるパターンで多いのは、まだ自分はやり直せると考えているであったり、浮気してしまって配偶者より拒まれていたりということが多いかなというのが私の印象です。
これは一例ですが、様々な事例がありますので、状況に応じた対応が必要です。
解決事例
受任前
この方は、ご自身で離婚調停を行ったが、応じなかったためということで、もう裁判をするしかないことは理解しており、そのためにご相談頂き、一旦見通しを伝えて、理解を求めて無理であれば早期に離婚裁判しましょうということでご依頼頂きました。なお、この段階で既に相当の別居期間が経過しており、裁判になれば離婚が認められる可能性の高い事案でした。
受任後
受任後早々の段階で、相手方に離婚を協議で対応する考えがあるか、なければ裁判するしかないので回答を頂きたいとご連絡しました。その際に見通しまでお伝えしましたが、結局応じてもらえず訴訟することになりました。
解決に向けて
訴訟提起した期日の中で、早い段階で裁判官に確認したところ、私と同様の認識を持っていましたが、相手方は応じることはなく、結局判決になり控訴審まで審理が続くことになりました。
時間はかかりましたが、無事離婚が成立した事案です。
まとめ
相手方が拒んでもいずれは離婚が可能です。
ここまで本記事でみてきたとおり、離婚に際して、別居期間がその事由に含まれていることから分かる通り、離婚の理由として別居期間の要件が充足すれば離婚は成立します。このように知っているか知らないかの知識部分も少なくないので、それで損をしないようにポイントを押さえておくことが必要です。
したがって、他方配偶者である夫もしくは妻が拒んでいるからといってあきらめる必要はありませんので、ご自身の今後の人生の為に何をすべきかをしっかり考えられることが大事です。
何を優先するかを考えて進めましょう
相手方が拒んでいるとなると、状況・事案にもよりますがある程度時間が掛かることも少なくありません。そのような中でより早く進めるためにできることも少なくありません(例えば、他の条件を譲歩する等です)。弁護士と相談して、相手方が拒んでいる中で何をすることで早期実現できるかを一緒に考えて進められることを強くお勧めします。中村法律事務所でも初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
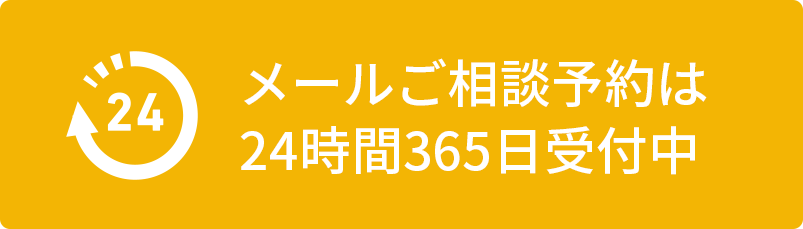

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。