離婚調停で弁護士は必要?後悔しないための完全ガイド
離婚離婚調停は、感情が絡むため思わぬ不利な合意になりやすい場面です。
弁護士を味方につけることで、法的視点から冷静に判断でき、納得のいく解決を目指せます。
目次
離婚調停とは
はじめに
離婚調停(りこんちょうてい)とは、夫婦が離婚に関して合意できないときに、家庭裁判所の「調停委員会」が間に入って話し合いを進め、合意を目指す手続きです。正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれます。
多くの場合、婚姻期間中における他方配偶者及びこの生活費である婚姻費用も同時に進められることが多いですし、必要に応じて婚姻費用調停についてもご説明します。なお、婚姻費用分担調停が正式名称になります。
離婚調停での協議事項
離婚するか否か
親権(共同親権によってこの部分は変動する可能性が高いと思われます)
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
年金分割
関連事件であるが婚姻費用
離婚調停に弁護士は必要か
例外的な場合を除けば、必要です
離婚調停は、前述のとおり家庭裁判所が間に入った話合いで、「話合い」である以上、ご自身で進めることが可能であるように思えると思いますが、よほど例外的な場合を除いて、なかなか厳しいのが実情です。
調停の家庭内の問題を法律論のみでなく柔軟な解決を目指すという性質上、良くも悪くも双方が合意すれば、その内容で確定してしまいます。この合意自体について、いわゆる実務慣行に照らして、適当でないものであったとしてもそれほど裁判所の判断として、合意形成をしないということはないのが現状です。そうなると、不利にならない為にも、進行について検討してもらえる弁護士を就けることを検討すべきです。
また、これもよくみなさまからお聞きしますが、調停がなかなか進行しないという風に聞きます。私が弁護士不在の調停を体験することが事実上不可能なので、お話や介入後の様子を見た上での想像になりますが、協議を仲介する調停委員によってはなかなか整理が上手く行かず進行しないということも少なくないようです。
離婚調停に弁護士が不要な例外的な場合
この場合も一度法律事務所に相談したが方が良いとは思いますが、離婚調停に弁護士が不要な場合は、離婚だけを望んで他の財産について全く不要でかつ一定の時間を要してもやむを得ないと言える場合かと思います。この場合は、離婚を相手方に要求して頂くことを続けることも良いのではというのが私の所感です。ただ、できるだけ早期に離婚を実現したい場合は、弁護士への依頼を検討されることを強くお勧めします。
実際に私が対応した事案でも、当初何ら財産が不要であるからできるだけ早期に離婚をされたいと仰ってご依頼頂いた女性の方がいらっしゃいました。この方について、一度お手紙を相手方に送ったものの相手方より返信がなかったので、離婚調停と婚姻費分担調停の申立てを行いました。初回は相手方も離婚を拒絶しておりましたが、その後第2回期日少し前に相手方にも弁護士が就き、事前にその弁護士と協議をした結果、早期に離婚に至ることができました。その中で離婚だけでなく、一定の金銭の支払いを受けることもでき、結局弁護士費用以上の支払いであったので依頼者様は手出しがないだけでなく、一定の金銭給付を受ける形で解決になりました。そのお客様に、早期離婚だけを目的にご依頼したのに、結果として、金銭給付も受けることになって驚いているし感謝していると言って頂けたことが今でも印象に残っております。もちろん結果はどうなるか分かりませんが、弁護士を就けた際の見通しを弁護士に確認することのデメリットは相当少ないので、離婚調停、婚姻費用調停に際しては弁護士に早期に相談されることをお勧めします。
離婚調停の進行について
基本的に、2名の調停委員と調停官によって進行されることになり、当事者が交互に調停委員に自身の考えを伝え、相手方にそれを伝えるということを何セットか繰り返すことになります。
調停委員とはどのような人か
基本的に男女1名ずつの一般市民と言われております。もっとも、裁判所のホームページによると、以下のように記されています。
社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
私の経験上、通常の離婚事件で、調停委員に弁護士委員が選任されることは少ないイメージで、相続事件や複雑な計算が絡む事件の場合に弁護士委員が調停委員として選ばれるイメージです。特に家事調停においては、裁判所が述べる「地域社会に密着して幅広く活動してきた人」が選任されることが多いように感じます。
調停官とはどのような人か
調停官は、分かりやすく言えば、裁判官です。裁判官が進行について、調停委員に進行についての裁判官自体の考えを伝えた上で、それに沿って進行するとみて頂ければと思います。場合によっては、調停官である裁判官が調停に入ってその考えをすることもありますが、調停官自体も同時に相当数の調停の調停官を担当しておりますので、なかなか厳しいのが現状です。もっとも、私自身は、あまりに当方の考えが調停官に伝わっていないという場合には、調停官と直接話をさせて欲しい旨を伝えることもあります。
離婚調停に弁護士を依頼するメリット
調停への同行で安心
調停への参加が認められているのは、当事者本人及び代理人です。代理人は、基本的に弁護士と思って頂ければと思います。特に、裁判所の許可を受けたものといった規定になり、弁護士以外の代理人も認めておりますが、弁護士以外の代理人の選定は難易度が高いと言われております。
自分の考えが伝えにくいから親であったり、子ども、仲の良い友人に一緒に入ってもらいたいと希望する方もいらっしゃいますが、なかなか厳しいのが現状です、
弁護士と一緒に調停に挑むことになると、調停委員に自分の考えを伝えることができるか不安な方はそこの払拭が可能ですし、十分な進行が期待できるかと思います。
その意味で、無駄な長期化を防ぐこともできますし、やるべきことを調停で進められるという点で、まずもって弁護士に依頼するメリットといえるかと思います。
法的見通しを確認、理解しアドバイスを受けながら進めることができる
調停の進行の中で、合意するか悩んでいる際に、離婚訴訟になった際に裁判所が出す結論との際をある程度確認しながら進めることができます。これについて、裁判官と弁護士は基本的に、似たような感覚、考えを持っていることが多いですので、ある程度先を見据えて、現状と比べてどうなのかといった判断をしやすいと思います。例えば、現状の整理で500万円の給付という状況で、裁判上の整理をした場合に450万円程度になった際、その50万円の差額をどうするかという視点で考えることができるかと思います。実際に450万円の給付という現実が分からなければ、500万円の給付で納得できるのかというところを法律上の帰結とは別にいわば「なんとなく」判断するしかないということになりかねません。
また、離婚調停と並行して行われることになることの多い婚姻費用分担調停については、特にこの見通しが重要であると個人的に思っております。婚姻費用分担調停については、調停での解決ができなかった場合、「審判」といった手続きに移行します。この「審判」という手続きは、いわば調停と裁判の間のようなもので、調停で審理の対象になった資料およびそこから追加資料を前提に審判官(裁判官です)が判断するという手続きです。家庭裁判所によりますが、調停に調停官として対応した裁判官と審判官として対応する裁判官が同一の方であることも少なくありません。そうなると、調停の段階で裁判官の考えを確認しておくことで、審判での審判官での判断を事前に確認して、審判に移行するのか否かを検討することができます。それこそ、審判移行するより優位な内容で調停合意した方が依頼者様にとって意義があるのではないでしょうか。その意味で見通しの十分な把握は弁護士を就ける大きな意味であると思います。
対応すべき範囲を明確にすることが可能です。
よく調停中に対応を相談に来られる方が言われることとして、調停でこのようなことを求められているのですが、本当に対応しないといけないのでしょうか。といったご質問が少なくありません。その際に私の経験上、本当に対応した方が良いものもあれば不要じゃないかというものもあるといったところなのが正直なところです。よくあるのが、相手方本人の意向が強く、調停委員がその意向を踏まえて対応しているといった状況です。経験上多いのが特段何か収入状況が変わっていないにもかかわらず給与明細の提出を求められたり、直近を超える期間の預貯金明細の提出を求められたりといったものです。
一般論としてですが、収入状況の変動がなければ、年間の想定収入が分かる所得課税証明書や源泉徴収票の提出は必要ですが、直近の給与明細等を必ずしも必要という訳ではありません(もっとも、状況によっては提出の必要があることもあります)。また、預貯金明細について、婚姻期間全体のものの提出が必要なことは双方合意の下といった例外的な場合を除いて必要がないのではというのが私の考えです。
以上のように調停で求められたからといって、必ずしも対応する必要がありませんし、不必要な資料の提出で、ご自身にとって不利になることもありますし、調停合意が遠ざかることも少なくありません。その点について、弁護士がいれば何の対応が必要か、何の対応が不要であるかをちゃんと見極めることで、ご自身にとってより良い解決をつなげることが可能です。
調停の中で必要な調査が可能です。
調停の中で、相手方が必要な資料を提出するのであればよいのですが、これに対応してくれない場合、請求側が資料収集を行わない限り、その資料を裁判所が独自に調査をしてくれるということは基本的にありません。そうなると、調査をする資料について、本当に必要なものを請求する側がその資料の調査の有無を検討して、場合によっては、裁判所による手続(調査嘱託といった手続きや文書送付嘱託といった手続きです)を申立てることが必要です。これについても、法律上裁判所の職権でも行えることになっておりますが、事実上、当事者からの申し出がないと現実裁判所が独自に行うことは少なくないのが現状です。
例えば、収入資料が出てこない場合は、それに相当するものを調査の対象にするであったり、財産分与対象財産の不足が疑われる場合は、金融機関に調査を行ったり、相手方職場を対象に調査を行うということをこれまで行ってきましたし、現実として、それによって分与を受けるべき金額の整理を行うことができることになります。また、実際に調査嘱託の申し出を行うことで、相手方に少なくとも裁判所から手続の内容が説明されることで、実際に職場や金融機関に連絡がなされるといったことが通知されます。そうなると結局調べれるぐらいであればということで、相手方が任意に資料開示をなされることも少なくありません。
私の経験で調査嘱託を申立てて、相手方より資料の任意開示があったことがほとんどですが、過去には、ほとんど金銭に関する資料がない状況から、別居時に把握して頂いた情報を基に調査嘱託を行って、それによって3000万円以上分与額が増額した事案もありました。
このようにやるべきことを行うという意味でも弁護士と調停対応するメリットかと思います。
オンラインでの対応が可能です
昨今のオンライン化の流れを受けて、調停手続もオンライン化されております。ただ、調停手続が非公開であることから、ご本人が調停に参加する場合は、遠方の裁判所で調停が開催される場合、直接出頭するもしくは場合によっては、近くの裁判所に出頭してオンラインで対応することになります。他方で、弁護士が代理人として対応する場合、代理人事務所で対応することも可能です。調停手続の待ち時間が長いことから代理人事務所で対応できるだけでもメリットはありますし、相手方との接触を可能な限り避けるということも可能です。また、遠方の裁判所で近くの裁判所でのオンラインの対応ということになれば、オンライン対応の為に向かう裁判所の空き状況の確認ということも必要になり、なかなか期日の調整が困難ということになりかねず、その点から解決までに相当の時間を要するということになりかねません。
弁護士同士の期日及び期日外での交渉・調整が可能です。
一方の当事者に弁護士が就けば、他方当事者に弁護士が就くケースが多いです。多くの弁護士は、双方が良い形で解決することが良いと考えていることが多く、そうなると期日や期日外でいわゆる実務慣行に沿った調整を図ることが可能です。
よくあるのが、調停になるとその期日の中では相手方代理人と直接話できることはないので、期日外で、相手方代理人と調整した上で、解決できる条件を整理するということも少なくありません。その整理が上手く行った場合は、裁判所に双方で条件面の整理ができたことを連絡した上で、成立させることも少なくありません。
少なくとも、双方代理人が就いて、調整を図るため調停前で十分中身を確認した上で解決できる、内容整理し次回期日で再度確認というものとは異なり1期日分早期に解決できるといったメリットがあるかと思います。
この点は、確かに相手方弁護士次第という面は否めませんが、このような形で解決することで、みなさまにとってより良い解決という意味で弁護士を就ける大きなメリットかと思います。
弁護士を就けることのデメリット(費用面)
これについては、おそらく費用面が唯一のデメリットかと思います。ただ、前述の挙げた例のように弁護士費用を考慮しても経済的メリットが大きい場合も少なくありませんし、整理する負担や見通しが不明な負担、解決までの時間が長期化することを考えると、費用面と比較して弁護士に依頼することも検討した方が良いのではというのが私の考えです。
弁護士依頼が特におすすめなケース
財産分与の必要がある方
離婚調停で財産分与の整理をするとなると、多くの場合、弁護士が介入することによる経済的メリットが弁護士不介入の時より大きいです。加えて、財産分与については、基準日(一般に別居日であることが多いです)の財産を双方エクセル表で整理して、分与すべき金額を定めることになります。なかなか慣れがないと難しい分野で、ご自身で対応するとなると相当方法を調べる必要があるかなというところです。
以上より、財産分与を行う必要がある方は、調停を弁護士に依頼することを検討される方が良いかと思います。
DVや相手方の浮気・不倫で慰謝料を請求したい方
慰謝料の請求については、まずその行為の特定、損失の主張、相手方反論への対応が必要になります。その上で、調停の中で相手方に納得して金銭の支払い合意まで受けるためには(調停は双方の合意を前提に調整を図るものですので、合意を取ることが必要です)、こちらの主張に納得させることが必要です。
よく言われている内容としては、実際の事実まで知っていないとできない主張の程度に具体的な話をするであったり、客観的な裏付けを出すというものです。私の経験上、そこまでしても相手方が調停の中で支払いの合意をするかしないかその時によるということになりますが、そうなった場合訴訟等で払わせる手続を進めるかといった点も含めて、弁護士と進める必要性が強い事項があるかと思います。
相手方によるモラハラを受けていた方
モラハラをする方は、私の経験上ですが、得てして自分の独自の論理で相手方に強く迫ったり、相手方が合意するまで執拗に迫ってくる方が多いです。そうなると、得てして調停の中でも同様な主張がなされることが少なくありません。調停委員もその仕事上、相手方の主張を伝えざるを得ず、それをご自身のみで聞くのも相当のご負担かと思います。そのような相手方と対峙するには、その相手方発言の真意等を弁護士に確認しながら進める方が、心理的負担は相当軽減できるかと思います。
性格が優しい方
これも進行の方向性が正しいかご確認されるお客様がよく聞かれるものとして、相手方がこう言っているもしくは調停委員がこう言っているから合意した方が良いのですかというものです。
相手方はあくまで相手方の主張ですし、調停委員は調停委員で調整するために働きかけを行っているに過ぎません。得てして、優しい方が相手方主張や調停委員のお話をのみ込んで合意しかねません。そのご質問時に相当不利な内容で合意しかけている方も少なくないですし、その内容が実務慣行に沿っていないということも少なくありません。
性格的に優しい方がご自身で調停を進められると、相手方に有利な内容で合意してしまいかねませんので、弁護士と一緒に進められることを強くお勧めします。
協議の際もしくは調停で進展がなかった場合
これまで相手方との協議での進展がなかった場合、ご自身で進めて十分な結果が得られる可能性は正直それほど高くありません。これまで、十分な対応をしてこなかった相手方が急に対応するということは考えにくいからです。
その場合の対応として、進展がない中でこの内容であれば合意できるものというのを提示するもしくは調査の余地があるのであれば、その部分の調査をすることが必要になってきます。これらの見極めを行った上で、かつあまり調整しても仕方がないと割り切って、裁判に移行する判断が必要になってきます。
上記のように進展がない場合は、進展がない中で進めるにはどうするか、次の進行についてどうするかを検討する余地があるので、弁護士と調停を進められることをお勧めします。
調停で依頼する弁護士を探す方法
離婚事件に対応する弁護士は、基本的に離婚調停に対応できるかと思います。
その上で、1度面談を利用して、弁護士との相性・進行について確認されることを強くお勧めします。
インターネット上の様子と実際の話した印象等は相当異なると思いますので、直接もしくはオンライン等でお話してみて、ご自身に合う弁護士さんを選ばれることをお勧めします。
調停を申し立てられると不利になるか
みなさまご心配になるようで、よく確認される事項ですが、これはなりません。
相手方が手続を進める意向があること、裁判所に納める費用の負担をしてくれているなといったことを把握して頂ければと思います。裁判手続きにおいて、手続を起こした方が裁判所への提訴手数料及び郵便切手を納める必要があるので、その負担を相手方が行ってくれたと考えて頂ければと思います。
これも繰り返しになってしまいますが、調停については、あくまで当事者双方の合意を目指す場に過ぎませんので、先に申し立てたから有利という訳でもありません。
ただ、調停を申し立てられてしまうと準備事項がありますので、それについての対応をしっかり検討して頂くことが必要です。
よくある質問
離婚調停について途中から弁護士に依頼することは可能か
可能です。
正確に数えたことはありませんが、途中からのご依頼の方も少なくありません。調停はお話合いですので、終局的な合意さえしなければ、途中からでもお話をすることができます。ただ、途中から入った場合、今までの議論をなしにして一から話をすることが少なくありませんので、今まで進められた調停が無駄になりかねません。その点から、早い段階でのご依頼を考えた方が良いかもしれません。
弁護士が入ると手続上何が変わるところがあるか
あります。
これまで挙げた一緒に対応するといったところ以外にも、最初の手続説明のオリエンテーションが無かったり、調停委員によっては、弁護士が就いているので主張を教えて下さいと言われたり、仕事の都合の場合、弁護士に対応を任せることができると言って点で変わってきます。
調停はどれぐらいの頻度で行われますか
概ね1か月から1か月半に1回で期日が入ることが多いです。
もちろん他の事件との関係での裁判所の込み具合や夏季休廷期間、正月期間等はもう少しかかることが多いです。
調停は何回ぐらいなされることが多いですか
これは、弁護士の進行に大きくかかわるところですが、私としては、細かな調整で期日が掛かっている際を除いて、5,6回で解決ができない場合、これ以上の進行が望めないと判断することが多いです。
そうした場合、調停を不成立にして、場合によっては離婚裁判への移行への検討をすることになります。
1回の調停で何時間ぐらい期日がありますか
これも裁判所によりますが(各家庭裁判所によって運用が異なります)、基本的には、自分の順番、相手方の順番で2セットぐらいなされるイメージです。多くの場合、2,3時間といったイメージですが、状況によっては長引くことや早く終わることも少なくありません。
解決事例(中途からの調停で状況が変わった事案)
ご依頼前
私が入る前も相当回数をやっており、相手方に代理人が就いているがなかなか進行しないといった状況でした。相手方が財産分与を求めているが、財産の整理が進んでいないといった状況でした。ご本人曰く、相手方が資料を出ておらず、調停委員にそのことを話しても一切資料の開示はなくどう進めるべきか分からないといったことをお話されておりました。
ご依頼後
まず、ご本人から聞いた情報(特に不足資料といわれていた部分)について、書面で適示して、これらの資料を出すようにと調停内の書面で整理しました。そうしたところ、相手方より資料の提示があり、それを前提に再度財産分与の整理をおこなったところ、どう整理の上では、男性側でしたが、お子様名義の保険の関係で相手方より当方に分与を受けることができるといった事案でした。
実際の解決
そこでご本人と調整して、子どものこともあるから一定の譲歩はして、ある程度分与を受けることでの解決をといった話を受け、相手方に提案したところ、相手方もその内容であれば、応じることでできるといった結果になりました。
依頼者さんからは、自分で進めて全く進まなかったものが、数回で解決して驚いているまた結果も相当いいもので、もっと早く依頼していればよかったと言われたのが今でも印象に残っております。
多くの場合、やることをやれば終わることが無いと考えられていた事件も終わります。解決せず悩まれている方は、現状を確認させて頂き、その上で解決への手段を提案させて頂くことができるかと思います。
ご依頼とは別にお気軽にご相談下さい。
まとめ
ポイント
弁護士を入れると相場の理解や悩みの解決に向けて適切なアドバイスを受けることができるといった様々な点でメリットがあります。特に、解決に向けて考えを整理するのは重要な点が多いと思います。
最後に
離婚調停自体過去に経験したことがあるという方はそれほど多くないかと思います。そして、話を聞くと途中まで進んだけど、よく分からなかったと言ってご相談に来られる方も少なくありません。その段階から介入させて頂くと結局それまでの進行についてあまり意味がなかったことにもなりませんし、そうなるとみなさまの貴重な時間が無駄になってしまいます。
多くの事務所で電話からのお問い合わせを受けているかと思いますので、可能な限り早期にご相談されることを強くお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
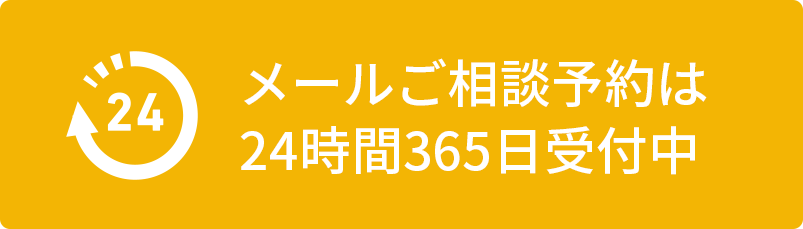

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。