【弁護士解説】離婚の親権者判断で「子の意思」はどこまで尊重される?―10歳を超えると意思が特に重視される理由を年齢別に解説―
離婚―10歳を超えると意思が特に重視される理由を年齢別に解説―
離婚で親権をどちらが持つか――。
もっとも重要な要素のひとつが 「子どもの意思」 です。
とはいえ、
「何歳から子どもの意思が尊重されるの?」
「親が誘導した場合でも影響する?」
「調査官はどこまで子どもの話を聞くの?」
など、疑問は尽きません。
この記事では弁護士としての経験をもとに、
年齢別の取り扱い・実際の調査方法・手続の流れをわかりやすく解説します。
目次
◆ 結論:10歳前後を境に「子の意思」は大きく重視される
離婚時に裁判所が親権者を決める際、
子どもの意思は重要な判断要素です。
- 6歳未満:ほとんど考慮されない
- 6〜10歳未満:参考にはするが決定的ではない
- 10〜15歳未満:非常に重視される
- 15歳以上:意思が最優先に近い扱い
と、年齢によって大きく違います。
親権・監護権の基本
■ 親権
離婚「後」における身上監護・財産管理を行う地位。
■ 監護権
別居中など「離婚前」に実際に子を監護する立場。
実務では判断基準がほぼ同じため、以下は共通して解説します。
親権判断の主なポイント
裁判所は、以下の事情を総合して判断します。
- これまで主に監護してきた親・その監護状況
- 現在の監護状況(安定性・継続性)
- 子の意思(10歳以上で重要)
- きょうだい不分離の原則
- 育児への関与度(性別ではなく事実)
- 面会交流に対する協力性
- 祖父母等のサポート体制(監護補助者)
特定の要素だけで決まることはなく、総合判断です。
年齢別|子の意思はどこまで尊重される?
■ 6歳未満
判断力が未熟とされ、意思は基本的に重視されません。
■ 6歳〜10歳未満
自分の考えは言えるが、
その考えが「どんな影響を受けたのか」を理解できていないことも多い年齢。
あくまで参考程度にとどまります。
■ 10歳〜15歳未満
この年代に入ると、意思は非常に重要になります。
- 生活環境を自ら説明できる
- 親に対する評価の理由も具体化する
など、根拠ある意見を述べられるため、
裁判所は強く重視する傾向があります。
■ 15歳以上
法律上「意見聴取が必須」。
実務上も、子の意思が覆ることはほとんどない年齢です。
子の意思はどう確認される?(家庭裁判所調査官)
子の意思の確認は、主に
家庭裁判所調査官(心理学・教育学の専門職)
が行います。
調査官調査の特徴:
- 親のいないところで話を聞く
- 話したくない内容は無理に記録しない
- 交流状況の観察が行われることもある
- 子の自然な気持ちが出やすい環境が整えられている
調査官の報告書は、裁判官の判断材料として非常に重要です。
親権争いの手続の流れ
協議
まずは話し合いで決めますが、親権は感情的になりやすいため、合意が難しいケースが多いです。
調停
第三者(調停委員)を介した話し合い。
しかし、双方が強く主張する場合は決裂することも多いです。
調査官調査が実施されることもあります。
裁判
裁判官が判断します。
調査官調査の結果や、実際の監護状況などを踏まえて結論が出されます。
親権争いで弁護士に相談すべき理由
親権取得の可能性を事前に判断できる
可能性が低い場合、別の解決策を検討するメリットがあります。
手続の「最適なタイミング」がわかる
調査官調査をいつ求めるか、交流実績をどう積むかなど、戦略が必要です。
子の意思を出すタイミングを戦略的にコントロールできる
子の意思を前面に出すべき時期は案件によって異なります。
親権と離婚条件(養育費・財産分与等)の関係
養育費
親権者側が受け取ります。
算定表では私立学費などは加味されませんので、交渉が必要な場合があります。
財産分与
親権との直接の関係はありません。
慰謝料
子の存在が金額に大きく影響することは通常ありません。
面会交流
裁判所は「原則として会わせるべき」という姿勢です。
しかし親権者が拒否する場合、実施までに時間がかかることがあります。
よくある質問
Q. 収入が高い方が親権を取れますか?
ほとんど関係ありません。
収入差は養育費で調整するからです。
Q. 調査官調査が不十分でした。即時抗告で再調査されますか?
可能性はあるものの、ほとんどの即時抗告は書面審理で完結します。
調査官意見よりも、調査結果の事実部分が重視されます。
解決事例
高校生の息子さん・中学生の娘さんと別居していた依頼者(父)から、
「子の意思を尊重したい」と相談を受けたケース。
- 調査官面談
- 面会交流の積み重ね
を経て、息子さんが「父と生活したい」と明確に意思表示。
最終的に母側もこれを尊重し、合意に至りました。
まとめ
親権の判断において
「子の意思」 がどれほど尊重されるかは、
子の年齢が非常に大きなポイントになります。
特に10歳を超えると子の意思が重視され、
15歳以上ではほぼ優先されると考えてよいでしょう。
親権は非常に専門性が高く、戦略性も求められる分野です。
お子さまの気持ちを大切にしながら最善の選択ができるよう、
ぜひ一度ご相談ください。
無料相談はこちら

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
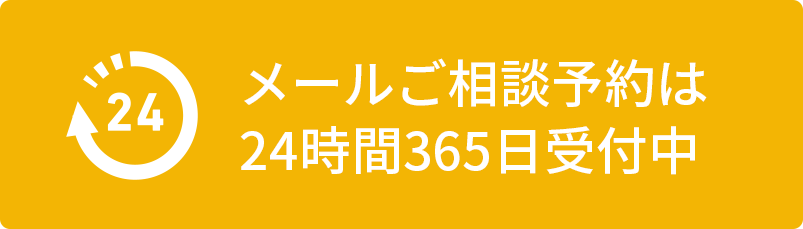

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。