面会交流を拒否されたらどうする?子どもの意向を理由とする際の対処法
離婚別居後もしくは離婚後子どもと一向に併せてもらえないといった方は少なくありません。それも、これまで子どもとの関係が良好であったにもかかわらず、子どもが会いたくないと言っているといったことを理由としてのものがほとんどです。そういった場合どう対応すべきか、面会交流事案について、これまで相当数対応してきた弁護士が取るべき手段を説明します。
面会交流とは
面会交流とは、離れて暮らす親と子が直接または間接的に交流する制度です。
裁判所も「非監護親からの愛情を実感する重要な機会」と位置付けており、正当な理由がない限り面会交流の拒否は認められません(東京高裁平成29年11月24日決定)。
裁判所が面会交流制限するケース
裁判所は、子の福祉を最優先に判断しますが、面会交流自体を行うべきでないといった判断をするのは相当限定的です。基本的には、①子の連れ去りや子への暴力の現実的可能性②子の意向といったところが前提になってきます。
① 連れ去りや暴力のリスク
これらの判断は、まま主張されることがありますが、裁判所としても抽象的な可能性を前提に判断することはなく、具体的な可能性があるかといった視点で事実認定をすることになります。同居中のなんとなくの恐怖心から認定されることはほとんどなく、実際に何があったかであったりとした事情を踏まえて判断することになります。虐待に類する行為があり、そのことが証拠上明らかになるとこの観点から厳しいといったことになりかねません。また、配偶者に対する暴力があるような場合も子の健全な成長にとって阻害事由となりかねないとして裁判所が認めない可能性もあります。
またよく言われる連れ去りも、例えば親権者が明確に決まっている段階で連れ去りのおそれがあるとか法的手続きがなされている中で現実的な危険性があるとかといった観点で具体的に判断がされることになります。
② 子どもの意向
どちらかというと面会交流ができなくなるのは、こちらの要件がネックになることが多いです。現実に子の意向を基に判断するとなると10歳を超えたところからになります。もっとも、年齢が低かったとしても子が面会することを望んでいない場合は、現に面会を行っても面会交流の意義である非監護親の愛情を伝えることはできませんので、その意向が現実のものであるか(監護親がそのように伝えることが少なくないです)、仮に現実であるとすれば、どうすれば払拭できるかを考えていくことが必要です。
面会交流を拒否されたときの対応ステップ
弁護士へ相談
面会交流は、感情的な対立が原因となっていることが多く、一度面会交流が拒否された中で法的手続きによらずに面会交流を実施することは難しいです。そうなると、調停・審判になった際の見通しを踏まえて、対応を検討する必要があります。ご自身の事案で調停・審判と進めるとどのような方向に進む可能性が高いのかをこの分野に慣れている弁護士に確認されることを強くお勧めします。
面会交流調停の申立て
理由としては、結局任意での対応はなかなか厳しいです。そうなると第三者的立場たる裁判所の働きかけで進めていく外ないと思います。
面会交流を阻害する要因がなければ、裁判所が相手方に対して面会交流を行うよう求めることがありますので、それを踏まえた対応を考えるべきです。
早期の調停申立をお勧めします
弁護士と行うかはともかくある程度早い段階で面会交流調停を行うべきです。任意に交渉に応じない相手方に対して、面会交流の対応をすることは考えられないというのが正直なところです。
その調停の中で、相手方が面会交流を拒んできた理由を確認して、それに応じた対処を検討すべきです。
特に、子が会いたくないと言っている場合については、本当にそうなのかというところを子の意向調査を行う専門職である家庭裁判所調査官によって十分な調査をしてもらう必要があります。また、調停委員会によっては、早い段階で試行的面会交流を踏まえた判断をしましょうとなることも少なくありません。そこまで行くと、相手方要望のみで面会交流ができていない(実際に子が拒否していないという趣旨です)場合は、この段階で相当裁判所が相手方に対して説得することが多い印象です。
面会交流審判への移行
ある程度調停における調整段階で裁判所も子の意向が判明した場合で、それでもなお相手方が面会に応じない場合は、ある程度の段階で審判に移行するかと思います。
上記の顕出(調査官調査もしくは試行的交流で子の意向として面会をしたくないという意向が出なかった場合です)ができていれば、面会交流を実現できる方向の審判を行ってくれる可能性が高くなるかと思います。そういった意味でも、上記の調査官調査もしくは試行的交流の実現ができるかが重要になってきます。
再度の調停もしくは審判
上記審判が出て、ある程度面会交流を実施するような内容のものが出ても、相手方が応じない可能性もあります。
そうなると、1回目の審判で相手方が対応している中で(調停すら対応しないような場合は間接強制を認めるような内容の決定が出る可能性もあります)、いわゆる間接強制を認めるような内容が出ていればともかく、そうでなければ、再度の審判を受ける前提で調停もしくは審判を申立てて間接強制が可能な内容での面会交流の審判を行ってもらうことが必要です。
ここでいう間接強制は、履行(本件で言う面会交流)を間接的に強制するために、一度の不履行ごとに●万円の金員を相手方に支払う必要があるというものです。そして、間接強制を認めるような内容の面会交流の条件は、相当具体的な特定まで求めるのが現実の裁判例です。一般的に言われているのが、日時、場所及び実施方法が具体的に特定されることが必要です。現実の運用では、相手方が一応の対応(調停もしくは審判への出頭等)をしている限り、ここまで具体的な判断をしてくれるかが読めずそうなると、1回目に定められた面会を相手方が履行しなかったと主張し、その上での再度の審判を求めることになります。もちろん、初回から裁判所が間接強制可能な内容を認めてくれればよいですが、そうならなかった場合は、このような方法を考えておくことも必要です。
その後の手続(間接強制・強制執行・慰謝料請求・親権者変更)
ここまで進むことはあまり考えたくはないですが、具体的な内容の面会交流ですら応じない場合、間接強制の申立て及びその後支払われなかった金銭に対して強制執行を行うといった流れです。
それですら対応されない場合、面会交流が阻害されたことに対する慰謝料請求、面会交流に対応しない相手方が親権者として不適格であるという主張で親権者変更を申立てることも考えられます。もっとも、この辺りについては、実際の三年も含めて対応を検討する必要があるので、経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。
面会交流手続を弁護士に依頼するメリット
すべき主張、すべきでない主張が整理できる
特に面会交流で過剰に相手方を刺激することは子との交流という点ではメリットがありません。相手方への思いがあるにせよ、むやみやたらに相手方を刺激してもその点を裁判所が考慮しかねないので十分な注意が必要でその辺りについて、弁護士と相談することができる点がまず大きなメリットかと思います。
進行について十分な主張を行うことができる
裁判所も当事者からの申し出がないと調査官調査による子の意向調査や身上調査、試行的交流を早期に実施しないことが多いです。そういう意味でも早期実施の必要性や強く主張することで早期の進行(特に面会交流では子との継続的な交流という意味で意義が大きいと思います)が気合できます。
これは、調停や審判の結果に大きく影響しますので、弁護士に依頼する意義が大きいと思います。
面会方法の内容を一緒に考えることができます
経験のある弁護士であれば、相手方が懸念している点を考慮すればこういった内容の面会であれば双方実現できるのでは、といった提案を複数持っています。それを前提に調整が上手く行けば、早期の面会につなげることができます。
よくある質問
Q解決までどれぐらいの期間がかかるか
少なくとも半年、1年程度は考えておくべきです。
早期に進行できるに越したことはありませんが、非監護親と監護親で感情的対立、どちらかといえば、監護親の感情の問題がある場合が多くそうなると、試行的勾留まで行かないと面会の実現まで進まないことが多いです。
そして試行的交流を行うとなれば、裁判所の場所の調整、事前の調査官による心情調査があることも多く、そうなるとどうしても時間が掛かってしまいます。
Q調査官調査で子の意思として交流を嫌がっていると判断された場合はどうすべきか
あくまで私の考えですか、その場合は間接交流から慣れさせていくことを考えてよいかと思います。子の利益に叶う形で進めていくべきです。
間接交流とは、対面で会っての面会でなく手紙や電話・ビデオ通話等を通した交流です。
Q弁護士に頼むべき基準が分かりません
もちろん弁護士費用の問題がありますが、そこを問題にしないのであれば、相手方が任意に面会交流に応じないのであれば、弁護士に依頼することもご検討すべきかと思います。
Q元配偶者が再婚した場合は面会できないのですか
基本的に、裁判所は両親双方から愛情を受けていると感じることが重要と考えております。そういう意味でも、再婚の事実をもって面会できないと考えるべきではありません。
面会交流は子の重要な権利ですので、それを実現できるよう動くべきです。
Q直接交流を相手方が応じてくれない場合どういった対応が考えられますか
例えば、間接交流機関を利用する等双方が歩み寄った形で交流を継続することが重要です。
Q相手方が面会交流に対応をしてくれなくても養育費は支払う必要があるのですか
支払う必要があります。
面会交流と養育費は交換条件と裁判所は見ないので、支払う必要があります。
解決事例
受任前
父親側のご依頼でしたが、いわゆるいきなり子どもを連れて県外に行かれてしまったという事案でした。ご本人とお話し、引き渡し請求の申立ても検討しましたが、見通しを踏まえて、子との早期面会の実現でご依頼を頂きました。
受任後
ご本人からの事前の聴取でもお子さんとの関係は良好であったことからその前提で、早期の交流を求めましたが、相手方は子が嫌がっているといういわばこの種の事案でよくある回答で面会の拒否をされました。そこで、これ以上話しても仕方ないと考え、試行的交流の実施を強く求め、裁判所・家庭裁判所調査官も理解を示してくれ、比較的早期に実現できました。おそらく調停申立後6か月程度での試行的交流が実施でき、これ自体は相当うまく進行できた事案です。
結果として、試行的交流で父親と子の親和性を顕出することができ、その次の期日で調査官から相手方への強い説得が入って、無事直接的な交流を実現することができました。
本件を振り返って
本件が早期に実現できた理由は、早期の試行的交流の実施です。もっとも、その進行の上で、子との関係性が問題ないことを確認できたのでこういった方法をとることができましたが、状況に応じた対応が必要です。
どう進めるべきか悩むところが大きいですが、本件は依頼者様も私を信頼してくれ、進行に納得してくれたこともあり上手く進行できた事案であると振り返っても思うところです。
まとめ
自分の子と会えないのは、何ともいたたまれないかと思います。やれることを行わないといつまでも後悔が残ることになる可能性が高いです。
他方で、事の性質上相手方との調整が必要なものでもありますので、しっかりと約束事を守ってすするという意識が必要になります。
進行や主張のポイントについて慣れている弁護士とそうでない弁護士によって違いがあるので、しっかりと方針を確認の上、ご自身とお子様の交流のために、愛情を実感する機会とされるよう検討されることをお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
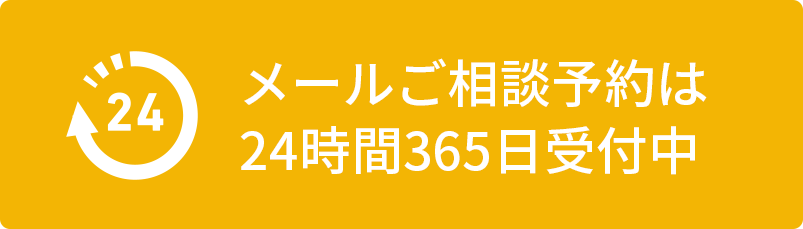

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。