【弁護士解説】離婚で父親が親権を取るのは難しい?判断基準と実際の事例
離婚目次
親権とは?父親が知っておくべき基本ルール
親権の定義
法務省のホームページによると、「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
親権の判断
いわゆる家裁裁判所の判断基準を踏まえると、
①従前の監護状況
②現状の監護状況
が主たる判断基準になると言われております。もちろんその他の考慮要素も存在しますが、特に上記2点を踏まえた判断になります。
なぜ父親は親権を取りにくいのか【裁判所の判断基準】
仕事で従前十分な監護ができていない
夫婦関係悪化の前の円満な段階で、多くの夫婦が役割分担として、父親が主として仕事を行い、母親が育児をしていることが少なくないかと思います。そういった点からすると、主たる監護者が、母親となり、翻って父親がこの点でかなり不利に働いてしまうということになります。
継続的な監護が難しい
仮に従前の監護状況を別にしても、父親が別居後、仕事を行いかつ子の監護を行うというのがなかなか難しいという方が多くそこも理由かと思います。よく言われるのが男性の時短勤務や育児に伴う休暇に理解のない会社が多いためといわれておりおます。
監護補助者の存在
これはあくまで私の経験上に過ぎないのですが、主として監護を行っている母親が自分の親と交流を持ち、義理の両親とそれほど交流を持っていないということが現実には少なくありません。もっとも、距離的な問題等で父親側の方と頻繁に会っている場合等は、上記の考えが当てはまりませんが、一般論として上記の考えが言え、そうなると監護補助者との親和性という意味でも不利になってしまいます。
紛争激化に伴い、母親が子を連れて実家に行く可能性がある
現状の共同親権が導入されようとしている中で、継続した監護が望ましいという前提で仕事中に一緒に別居されかつそのまま十分な交流ができないといったことは望ましくないと個人的には思いますが、そのような場合裁判所は現状を尊重するというのがこれまでの考えです。親権制度に対する法改正が入ったところで審判に対する考えが変わるかは正直何とも言えませんが、この点もこれまで父親が親権取得するに際しての大きな弊害となるポイントでした。
父親が親権を獲得するために必要な条件
結論から言うと、上記で挙げたような取得しにくい理由となる部分を払拭できるかという点になります。こういうのは簡単ですが、なかなか現実としては、難しいのが正直なところでどう対処するかを考える必要があります。
まず十分な監護です(監護実績の構築)
私の相談の経験上、よく自分は監護をできているという方でも、せいぜい土日の監護をできているかなというところです。そうなると結局、平日と土日の割合になるので、5対2になり、主たる監護は母親側になってしまいます。その対策として、双方共働きで調整するとか、平日は夜間も含めて監護するとかといったことが考えられます。現実なかなか難しいですが、そういった方法が考えられます。
母親の監護より十分な監護を行うことが大事です
これもなかなか難しいのですが、母親による監護よりより良い監護がなされていると見てもらえるかです。現実的に監護の内容についてはある程度裁量があり、誰が見ても良くない監護を妻側がしてない場合厳しいのが正直なところですが、十分な監護を主たる監護者が行っているからこそその継続が望ましいと裁判所が考えているのでこの方法(母親の監護が不適切であることの認定)を取ることが有効といえます。
これらの例としては、例えば、相手方が監護せず不倫(浮気)を行っているや夜間子どもだけにしてどこかに出かけるや精神的に相当不安定、虐待などといったことが挙げられます。これらの立証自体相当困難なのは間違いないですが、これがあれば、父親が不利ということ自体は覆すことができるのではというのが私の感覚です。
監護補助者を含めた監護体制の構築
仮に親権・監護権を取得できた場合に、どのような準備ができるかはしっかりと主張することが必要です。父親がこれまで監護できた程度は多くとも半分程度のことが多く残り半分の監護分をどのように埋め合わせるかをしっかりと考える必要があります。
そのために何をするかをしっかり検討することが必要ですが、よく私がお伝えするのは監護補助者(ほとんどの場合両親になると思います)の同居を含めた体制構築まで考える必要があります。正直そこまでしても監護体制が構築できていると評価してくれるかは難しい面がありますので、最低限ここまでは考える必要があるかなというのが私の感覚です。
一定年齢を超える場合は、子の意思も十分配慮されます
少なくとも6歳程度まではそれほど子の意思が考慮されることはありませんが、これを超えて来てかつ年齢相応の発達をしている場合は、一定程度子の意思も考慮されます。そして、10歳を超えてくると、子の意思に重きを置いた配慮をすることになります。厳密に言うと、子の意思の形成過程も含めて判断することになるのですが、特段不合理なものでなければ、子の意思を踏まえた判断がなされることになりますので、子とのかかわりが重要になってきます。
まとめ
結局、母親より父親の方が監護者として子どもの教育・養育にとってより良いと思ってもらえるかどうかというところが重要になってきます。これがなかなか難しいのが父親の親権取得が難しいと言われる所以かなというのが私の印象です。
父親が親権を取れた実際のケース
一般的に言われているとおり、父親が親権を取得するのは難しいのですが、これまで述べた方法を前提にすると、親権を取得しえますし、父親側が親権取得をした事案は少なくありません。
主たる監護者を父親と認定した事案
これはやむを得ない面はあるのですが、主たる監護者雄認定には多くの場合、子と接する時間に考慮を置いてきます。その前提で、父親が育児休暇を取っている事案で母親が働いていた場合、主たる監護者を父親と認定しました。この件について、夜間の監護等まで詳しく見ているかかなり怪しいのですが、こういった認定の下、父親が主たる監護者として認定され、親権者も父親となりました。
従前の監護に問題があった場合
多くの場合にあてはまるとは言えないのですが、監護をしつつ他の異性と不適当なやり取りがありそれによって従前の監護状況に問題があると認定されたものがありました。正直これは、判断を行った裁判官が少し実務の大勢と異なる判断をした感は否めないのですが、従前の監護に問題がある場合はこういった判断になることは少なくありません。
その他、発育が不十分でありかつ主たる監護者が精神的に不安定であるといった事情がある場合はその点で父親側が親権取得という事案もありました。
子の意思による場合
この事案は、子が高校生であり父親と生活がしたいとはっきり述べかつそれについても十分合理的な理由付けができているという事案で、父親が親権取得したものもありました。
父親の親権取得に関するよくある質問
Q不倫(不貞行為)は子の監護権に影響を及ぼしますか
直接は影響しないのが原則です。
もっとも子の監護をないがしろにして不倫をしているといったような場合は、それこそ監護が適切に行われなかったといった判断になります。ただ、原則はそのような形ではありますが裁判官によっては、不倫を重く見る方がいなくはないのが正直なところです。その他、妻側による夫へのモラハラやDVについては、どこまで事情として考慮してくれるかは子への影響という観点で見てきますので、そこを踏まえた主張が必要です。
Q収入が高い方が親権を取得した場合の養育費は?
算定表をそのまま利用することはできません。
法務省が発表している算定表が多くの場合用いられるのですが、これは子を看ている方の収入の方が低い場合です。本件のように父親が親権を取得する場合はこれが当てはまらないので本算定表を用いず、少し複雑なものになるので注意が必要です。
Q父親が親権を取るには弁護士に依頼するべきですか?
依頼すべきです。
ただでさえ、親権を取得するのが難しいのが現状ですので弁護士と一緒にやれることをやるべきです。ただ、裁判所も何となく母親を勝たせているわけではなく、母親による親権取得の根拠があるので、これを父親側で満たすことができれば父親の親権ということにしております。そういう意味で何を主張すべきかの整理で弁護士に相談し、依頼すべきということになります。
Q親権争いの主戦場はどの手続きになることが多いですか?
多くの場合、離婚訴訟であったり監護者指定の審判であったりということが多いです。
まず、親権争いについて、その性質上協議による話し合いで、どちらかが認めることで調整することは、不利な父親側が諦めることを除いて少ないです。そうなると、裁判手続きでの争いでということが多いのですが、裁判所による環境調査(調査官よって行われます)の末、離婚調停で合意することも少なくありません。また、この調査の結果を踏まえて、双方歩み寄って面会交流をある程度調整することでの合意を図るということも少なくないのが現状です。
同様に、今ニュース報道でもある一方の配偶者の連れ去りについて、速やかに監護者指定の申立てを行うということも少なくありません。その中での決定が多くの場合、最終的な親権の決定となることになります。
解決事例
依頼前
父親側の事案で、いきなり裁判をされて、娘は母親になついているのでやむを得ないが高校生である息子の親権を取れないかというものでした。実際に別居後も(相手方が子を連れて別居しておりました)、子との面会を実現しており、その中で十分な交流を持てておりました。実際に本件の息子さんは、父親に色々と相談し、それに対して相談者さんも真摯に回答しておりました。
そのような状況でしたので、しっかりとお子さんの意思を顕出させましょうということでご依頼頂くことになりました。
受任後の対応
ご依頼後もこれまで通りの面会を行いつつ、後に行われた調査官調査では今後の監護体制についてどうするかをしっかりと準備の上話して頂き、お子さん自身も今後の生活について父親に相談したいとの話が出て、子の意思として父親との生活を望むというものがありました。
結果、父親側で親権取得という結果で終えることになりました。
本件を振り返って
ご依頼前から一貫してお子さんの意思を尊重したいといった考えがあったご相談者様でそれを踏まえて、無事親権を取得できて、この件の解決ができた時は喜びよりも安堵感が強かったのを覚えております。
父親が親権を取るためのチェックポイント
・子どもとの関わり(平日・休日を通じて)を十分に持てているか
・監護補助者(祖父母など)の協力体制を整えられるか
・母親の監護に不安要素がある場合、それを立証できるか
・子どもの意思を尊重できているか
まとめ
父親がどうしても親権で不利なのは間違いありません。それは現状の日本の社会の構成上ある種やむを得ないです。もっとも、不利なのは日本の社会の典型的な夫婦の場合であり、それと異なれば不利とは言えませんし、そもそも親権ということの性質上、不利だからやむを得なというものでもないと思います。自分が親権を取得し、監護する方が子のためになると考えられるのであればやれることをやるべきであると思います。
親権問題で悩まれている場合はお気軽に弁護士へ相談されることをお勧めします。
親権は一度決まってしまうと、簡単に変更はできませんので、十分な知識、流れについて、十分に理解した上で、進められることをお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
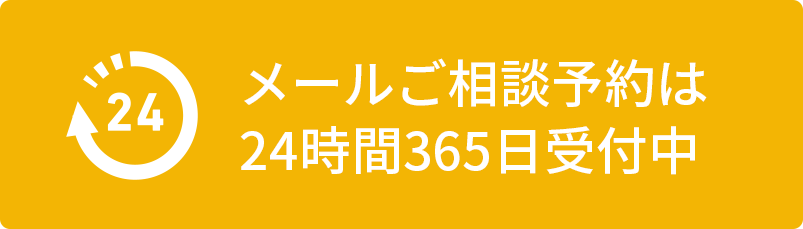

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。