親権放棄は必要?父が親権・監護権を得るための条件(2024年改正対応)
離婚令和6年(2024年)5月に民法改正が成立し、離婚後も共同親権を選択できる制度が導入されました(施行は公布後2年以内、遅くとも2026年5月まで)。ただし、自動的に共同親権に変わるわけではなく、単独親権を選ぶことも可能です。既に離婚して親権が決まっている場合は、原則そのまま維持されます。
この改正により、父母双方が子の養育に関わる機会は広がりますが、依然として「誰を主たる監護者とするか」が最大の争点となります。。そうなるとこれまでのように単独親権が前提といった議論が妥当しないのかもしれませんが、ただ監護者を一方として主たる養育についていずれか一歩になると思われます。
その観点で、父が監護権者となるには、母の親権(監護権)放棄が必要であるのかという点を見ていきたいと思います。
目次
親権放棄とは?正式な手続きは存在しない
「親権放棄」という制度は法律上存在しません。
ただし、実務上は「親権を相手方に譲る」合意がなされることがあり、事実上「放棄」と表現されることもあります。
実務で見られる「親権放棄に近いケース」
離婚協議の段階
将来の生活や養育環境を考え、相手方を親権者とする合意をすることがあります。
(例:養育補助者の有無や生活資金を考慮して父より母が適切と判断する場合など)
裁判・審判の段階
主張や反論を重ねる中で「子どもにとって父が育てる方が良い」と母が理解し、和解的に譲渡されることもあります。
父が親権・監護権を得るには?裁判所の判断基準
基本的に、裁判所は監護権の判断において、
①従前の監護状況
②監護の継続性を主として判断することになります。
私がご相談者様に説明するときは、①の言い換えとしてこれまでどちらが見てきたか、②今どちらが見ているかといった判断基準を取ることが多いといった説明をすることが少なくありません。こういった判断基準を前提として、他方親に連絡をすることなく、別居することが少なくありませんでしたが、共同親権の導入により、事前の他方配偶者の承諾のない別居はその点をとらえて不利に働く可能性もあるかと思います。
上記判断基準を踏まえると、お子さんが小さいときは特に女性が育児休暇をとることが多い関係もあり、従前の主たる監護を担うことも多く、それに問題がなければ、母親による親権取得という流れになることが多いです。この点から見てもですが、父親が育児休暇が取った場合等は、その点を十分考慮するのが裁判所の根柢の考えとしては、存在します。
上記が前提ではありますが、もちろんその監護に問題ないことが前提で、育児放棄や主たる監護者が精神的に問題があるといった状況等があれば、その前提が変わってくることになります。ここで難しいのがどの程度で監護状況に問題があるという点です。過去の私の経験になりますが、児童相談所への電話相談記録をもって、監護能力に問題ありとしている事案もあれば、他方で精神的な病状の事実認定があってもその監護状況には直接影響がないと判断した審判もあり、個々の裁判官の判断の差が非常に大きいところです。
以上のとおり、従前の主たる監護状況に問題がない前提で、主たる監護者でなかったものが親権(監護権)の取得となるとその権利の放棄で事実上進めることになります。また、これまで主たる監護者であったとしても今後の監護の継続が困難であれば、放棄という表現を使うかは別にして、相手方に今後の主たる監護をお願いするということも選択肢としてありうるかと思います。
母から父へ親権・監護権を譲るケース
父が親権・監護権を得るのは容易ではありませんが、以下のような状況では認められる可能性があります。
・母が育児放棄や精神的な問題を抱えている場合
・父が育児休業を取得し、実際に養育を担っている場合
・母が生活状況を考慮し、父を主たる監護者とすることに合意した場合
相手方に親権(監護権)を譲る上で考えておくべきこと
一度その合意すると変更は困難
基本的に、裁判所手続において、一度行った合意は相当尊重され、そこからどのような事情変動があったかという視点で問題をみることになります。
その点が前提ですので、仮に気持ちが変わったなどという理由では一度行った合意を覆すことはできませんし、変更するには相手方による虐待等の相当の事情が悲痛ようになります。
そこまで検討した上で、親権を譲るか否かの検討が必要になります。
養育費の支払い義務が生じる
「養育費」については、現に子を看ていない方から看ている方への費用の支払いということになりますので、法律上の整理では、あなたが養育費を支払うことになります。加えて、この場合、算定表を単純に適用するのではなく、やや異なった見方をすることになり(算定表自体、支払い義務者の方が収入が高いことを前提に作成されているものであり、これが当てはまらない場合は異なる見方をすることが原則です)、思っている以上に養育費の金額を支払うことになります。
ただ、現実として、養育費の支払いを請求しないことを前提にといった内容での合意のことも少なくありませんが、あくまで法律上の帰結としては上記の流れになりますので、その点については注意が必要です。
親権や監護権について悩んだ場合は弁護士への相談を強くお勧めします
見通しの確認が可能です
そもそも親権を取得できる可能性が高いのかそうでないのかといったことを裁判実務を踏まえて整理できるだけでも、事前に確認する意味は大きいと思います。そうすることですべき対処に対して十分な対策ができるように思います。
また、親権は見通しがあったとしてもそれに応じて必ずしも対応できるわけではありませんが、やるべきことをやるスタンスでいくのか、相手方の様子を見て考えるのかといった点で十分な見通しを持つことは意義のあるものかと思います。
メリット・デメリットを検討できる
例えば、親権争いに発展すると、長期化に及びことも少なくなく、そのデメリットをしっかり考慮して進めることが必要になります。また、本件のような親権放棄(ここでは権利を相手方に移すという意味で用いております)も他の部分で交渉上有利になることが一般的にあり得るのでそういった意味で、検討する余地があるかもしれません。
この部分でどうなるといった点でしっかりメリットデメリットを確認することだけでも弁護士に依頼するメリットは少なくないと思います。
よくある質問
Q育てていく自信がないので放棄した方が良いですか。
何が原因かをしっかりと考えた方が良いかと思います。
例えば金銭的問題であれば、相手方からの養育費であったり、行政給付で本当に厳しいのか具体的に考えた方がよいかもしれません。放棄(相手方の親権取得に合意)すると、取り返しがつかないのでしっかりと後悔の内容検討されることを強くお勧めします。
・Q親権を譲った後に後悔したら取り戻せますか?
原則として困難です。虐待や重大な事情がない限り、変更は認められません。
解決事例
受任前
本件は、母親が子どもを連れ去ったいわゆる連れ去りの事案で、父親側での受任事案でした。
ここまで本記事で述べたとおり、なかなか見通しが厳しいことをお伝えして、その点をご理解頂いた上で、監護者指定及び引き渡し請求を行うという前提でご依頼頂きました。
受任後
手続を進めていく中での調査等を踏まえて、裁判所としても従前の監護状況にも特に問題となるものがあるとは思えない、現状の監護も十分であるという前提での話が進んでおりました。
また、審判の最終盤の調査官調査でも当方に有利なものではなく、厳しい結論になるだろうと依頼者様とお話し、高裁への即時抗告も含めて協議をしておりました。その中での書面では、常にご本人がお子様に対して何をして何を考えているのかといったことを常に意識して記載するようにしておりました。
その結果が功を奏したのか、正直分かりませんが、相手方より何点かの条件と引き換えに当方を親権者する(本件は監護権者です)和解案を出して来ました。内容自体は、親権がこちらになるのであれば、調整可能であり、解決に至りました。
解決にあたって
正直このような事案は、ほとんどありませんが、あきらめず進めた結果かなと考えておりますし、何より依頼者様の思いが通じた結果であるとは思っております。
この件を通じて、どうなるか分からないということを改めて実感しました。
まとめ
・「親権放棄」という制度は存在しないが、実務上は譲渡に近い合意が行われることがある
・父が親権・監護権を得るには「従前の監護状況」と「監護の継続性」が重要
・一度合意すると変更は難しく、養育費の支払い義務も生じる
安易に放棄せず、メリット・デメリットを十分に検討することが大切ですので、親権問題で悩まれた際はお気軽にお問い合わせください。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
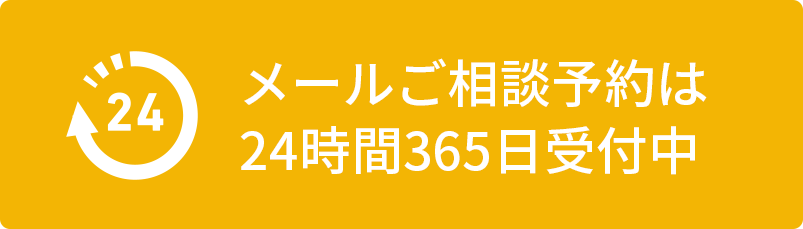

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。