離婚で住宅ローンが残っている家をどうする?財産分与の整理方法を弁護士が解説
離婚離婚で住宅ローンが残っている家をどう分けるか――多くのご相談で最も悩まれるテーマです。
「住宅ローンが残っていても財産分与の対象になるのか?」
「アンダーローン・オーバーローンの違いは?」
「名義変更や借り換えはできるのか?」
この記事では、弁護士が具体例を交えながら 離婚時の住宅ローン付き不動産の財産分与の整理方法 をわかりやすく解説します。
目次
住宅ローンが残っている家は財産分与の対象になる?
財産分与の基本ルール(婚姻期間中の財産は2分の1が原則)
婚姻期間中に夫妻で形成した財産(積極財産)を2分の1にする制度です。
住宅ローンと不動産の関係
財産分与の定義で述べるとおり、積極財産を2分の1にするものですので、住宅ローンがいわゆる不動産との関連性がある限りにおいて、財産分与の対象になります。詳細は後述しますが、多くの場合、不動産の現在時価と調整した上での整理を行うことになります。
アンダーローンの場合の財産分与(離婚で住宅ローンが残っているケース)
アンダーローンとは
不動産の評価額と残ローンを比べて、残ローンの方が少ない場合です。
計算方法
不動産の時価を出した上で、そこから基準時時点の残ローンを考慮し、整理することになります。
実際の計算
例えば、現在価値が3000万円であり、残ローンが1000万円である場合は、2000万円の価値があるとみて財産分与の整理を行うことになります。
オーバーローンの場合の財産分与(住宅ローン残高が家の価値より多いとき)
オーバーローンとは
基準時時点のローン残高が不動産の評価より大きい場合の整理になります。
大きな考えとしては、以下のものがありますので、状況に応じた主張が必要になります。以下では、自宅の現在価値が1000万で残ローンが2000万、他の財産を2000万円保有しているという前提でご説明します。
他の財産と通算する場合の整理
自宅自体、1000万円のマイナスになりますが。他の財産2000万円と通算して、1000万円が財産分与対象財産とするという考えです。
残った1000万円を500万円ずつに整理することになります。
他の財産と通算しない場合の整理
自宅のオーバーローン部分は、他の財産と通算、合計せず0とみて、残っている2000万円を整理することになります。そうなるとこの2000万円を1000万円ずつ整理するということになります。
裁判実務で多い考え方
財産分与として、負債が他の財産と通算されることもあり、一般に生活のための共同の債務などであれば認められることが多いです。そうなると自宅購入におけるローンは、生活のための負債であることは間違いないので、そういった意味では理論上は通算すべきであるという結論になるのかなと思われます。
ただ、実際の裁判で議論する段階になると、具体的事情等を考慮して調整として、特に離婚をはじめとする家事事件においては「その他一切の事情」を踏まえた判断がされることになり、そういった意味で本件の妥当性の観点から裁判所が判断することも少なくありませんので、理論上の帰結から安心して十分な主張をしないと思いがけない結果に繋がることになりかねません。
離婚時の住宅ローン名義変更と自宅の所有権整理
債務者がそのまま自宅を取得するケース
結局自宅にローンが残っている場合、どういう形で解決するかは、ローンを借りていることから債務者との関係でも十分調整することが必要です。
そう言った意味で、債務者がそのまま自宅を取得しかつ債務を今後も支払うのであれば、債務者としては当初の信用情報を前提に進めることになるので、問題なく進められることが多いかと思います。
債務者でない配偶者が自宅を取得し住み続けるケース
前提として、自宅を取得、所有者になるとなると現実的に、ローンの支払いを行うことに加えて、主債務者にならないとこの方向での解決は厳しくなるかと思われます。
名義変更や借り換えのハードル
この方法をとる際は、多くの場合主債務者であるローンの借り入れ先がこれを認めるかに依存してきます。そもそもの前提が元の債権者の支払い能力を根拠に融資しているので名義変更先の資力については考慮することになるかと思います。私の過去の経験では、相応の収入がありかつ離婚の条件調整で相応の現金に給付を受けた上で、財産分与の給付も相当程度受けたという事案で借換えができたものや親族が一括返済といった形であれば名義変更を行うことができました。いずれにせよ名義変更を望むには色々とハードルはありますが、それを一つずつ超えていく必要がありその上でも名義変更が必要かをしっかり検討する必要があります。
よくある質問
Q名義変更や借換えは可能であるのか
借換えを行う方の資力次第というのが結論になりますが、それであれば身も蓋もありませんので、あくまで私の経験上は以下のとおりです。
借換えを受ける方、新たに債務者となる方の収入が安定したものがあり(同年代の平均収入のイメージです)かつこれまで遅滞があるかないかといったところかなと思います。
もっとも、当然借換え先の金融機関によって変わってきておりその条件も厳しいところとそうでないところがあるのでいくつか確認されることを強くお勧めします。
Q. 住宅ローンが残る家を売却してから財産分与することはできる?
できます。
ただ、協力して売買手続を行わないといけない兼ね合いで書類のやり取りであったりの手間が増えること、売買までの期間が掛かるので時間が掛かってしまうというデメリットがあります。他方で、そうなった場合は、実際の売却代金を前提に、売買にかかる費用等の手続き費用も含めて考慮して財産分与の協議・整理に対する話し合いを行うことになるので仮定である査定金額を前提に進めることはなくなります。
Q連帯保証人になっている場合はどうなる?
これも可能であれば、離婚にともない名義変更を試みるべきです。
できなければやむを得ないですが、相手方が支払いを遅滞等してしまった場合、ご自身に請求が来ることになってしまいます。
Q通算説と非通算説が用いられる条件はあるのか
これはケースバイケースになります。
もっと言うと、論理的帰結ではあまり非通算説をとる説得的な理由がないのですが(なお、特にこのような場合は非通算で当然という場合はあるのですがかなり限定的です)、事情によって、非通算説が取られるということになります。事案ごとに裁判所が判断しているきらいがあるので、本件はこうあるべきだといった主張が必要ではないかと個人的に思っております。
Q住宅ローンを残っている家を取得すべきか
これはご自身の価値観かと思います。
特にどのような住居に住むかはライフスタイルの問題ですので、果たして、財産の大部分もしくは相応の負債を負って自宅に住むべきかはかなり悩ましい問題かと思います。
しっかりとメリットデメリットを考えて、後悔のない選択をされることをお勧めします。
解決事例
受任前
ご依頼者さんが女性で、収入状況はお子様が小さかったこともありそれほど大きくはない方で、最近家を建てたがもう相手方とやっていけないがどう家について考えるべきかといった内容でした。
本当に今後相応の負債を負ってお子さんと生活する上で家を取得したいか考えて下さいとお伝えしたところ、その負担は避けたいとのことでしたので、自宅を相手方名義に、本人も連帯債務にするということで方針が固まりご依頼頂くことになりました。
受任後
早速こちらの意向をまとめた書面を相手方に送付したところ、しばらくして相手方に弁護士が就きました。
その後、相手方が建設的な議論を行って頂けたうえで、元々の主債務者が相手方だったこともあり、相手方両親が協力することで、当方本人の名義を債務者から外す事での解決ができました。
解決にあたって
本件は、今後のリスク回避という点でできるだけ債務者から外すことを考えて交渉を進め、相手方代理人も協力して頂けて、このような形で進めることができました。
実際、相談に来られる方でも相手方がローンを払わなくなったことで自分が債務を払わないといけなくなる場合も少なくなり、ご本人も払えなくなり破産を検討せざるを得ないということも少なくありません。こういった形で自宅から伴うリスクを避けておくことをできればリスク回避になります。
まとめ
本件のように住宅が残る家をどう処理するかは、ライフスタイルの問題もあり難しい面もあるかと思います。
もっとも、選んだ方法で損しない為にはやれることをやるべきでありますし、種々の考えによって、あなたが財産分与によって取得する金額も大幅に変わってきます。
しっかりと整理して、損しない、十分な分与であったり整理するために場合によっては専門家に相談し、財産分与を行うことを強くお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
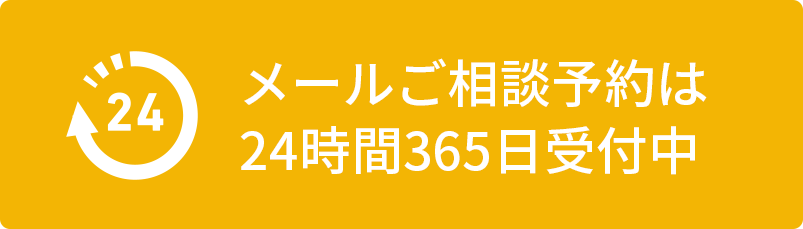

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。