離婚後も持ち家に住みたい方へ:名義・ローン・契約形態など重要な確認ポイントと対策
離婚離婚にあたって、「今の家にそのまま住み続けたい」と考える方は少なくありません。特にお子さんがいる場合や、生活基盤がすでにその家に根付いている場合、転居によるストレスを避けたいという思いは非常に自然なものです。
しかし、離婚後も持ち家に住み続けるためには、いくつかの法的・実務的な確認と準備が不可欠です。本記事では、実際に多くの事例に携わってきた実務経験をもとに、「離婚後の持ち家居住」について丁寧に解説します。
目次
離婚後妻が自宅に住むにあたっての確認事項
まず確認すべきは「自宅の名義」
最初に確認すべきなのは、自宅の登記名義です。具体的には次のいずれかのケースに該当するはずです:
・夫の単独名義
・妻の単独名義
・夫婦の共有名義
・どちらかの親など第三者が名義人
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで、簡単に確認できます。
- 夫単独名義だった場合の注意点
夫名義であれば、妻の意思に関係なく自宅を売却されるリスクがあります。そのため、自分の居住を安定させるためには名義変更や契約の見直しなど、対策が必要です。
住宅ローンの残債と連帯保証人の確認
次に確認すべきは、住宅ローンの有無とその残高です。ローンが残っている場合、主債務者(通常は夫)に支払い義務があり、支払いが滞ると家が差し押さえられ場合によっては競売リスクがあります。
あわせて、連帯保証人が誰かも重要なポイントです。保証人である限り、債務不履行時に請求がくる可能性があります。
妻が自宅に住み続けるための主な選択肢
はじめに
私の経験上、多く場合で持ち家の名義が夫名義の事が少なくありません。その場合の持ち家に住み続ける方法として、大きく分けると、妻名義に自宅の名義変更を行う方法(結局のところ財産分与で整理することになります)、夫名義のまま妻が持ち家に住む方法があります。以下ではそれぞれの方法について、確認していきたいと思います。
妻名義に自宅の名義変更を行う方法(婚姻中の財産分与における整理)
アンダーローン(残ローンより自宅価値が高い)の場合
この場合は、通常の財産分与と考え方は同じで、結局他の財産ではなく、自宅不動産を取得することになり、妻が終局的に不動産を取得するという事になります。また、本当に自宅を取得するということで良いのかといった点は検討する必要がありますが、アンダーローンになる程度にローン返済を行えている場合は、他にも財産分与対象財産があることが多く、そうなると妻側から金銭給付をしないといけない場合はそれほど多くはありません。
他方で、この場合は、自宅の価値をいくらでみるのかというところで、かなり分与対象の金額が変わってきますので、妥当な価値の算定がいくらであるのか(一般に価値の算定方法は複数あり、状況によって、固定資産評価、路線価、実勢価格等で使い分けること多いです)をしっかり見極める必要があります。
また、自宅の場合には、特に持ち家購入時に特有財産の支出について、どのような扱いにするのかという点も争いになりやすいです。ご結婚後すぐに自宅をご購入した場合、ご両親からの援助があった場合(どちらかというとこちらが多いでしょうか)について、特有財産をどう扱って、財産分与対象財産の整理の仕方について複雑な考え方があります。その点について十分な考え方をしないといわゆる実務慣行に比して、不利に扱われかねないので、注意することが必要です。
オーバーローン(残ローンの方が自宅価値より多い)の場合
この場合で、依頼者様から何とか持ち家に住みたいといった話になるとどう進めるか悩ましいなと考えることが多いです。以下で方法をご説明しますが、これが上手く行けばいいのですが、なかなかそうはいかないのが正直現実的なところです。
持ち家のローンを一括返済する方法
これができればまず問題ないのですが、残っている自宅ローンを離婚に伴って満額支払う方法です。多くの場合、ある程度のローンが残っていることが少なくありませんので、そうなってくると、完全に資力があるのか否かに依存します。それも、相応の資力があるかにかかってきますので、なかなか厳しいと言わざるを得ません。過去の私が対応した事案で、この方法をとることができたのは、ご両親の援助による方法で自宅を完済できたという方でした。現実的には、妻側にある程度資力があるのであれば、自宅名義の一部が妻名義になっていることも少なくなく、そうなっていない以上、ご両親から援助を受けることができるかという点に依存してくるかと思います。
借換えを行う方法
この方法もなかなか厳しい方法ではありますが、前述の一括返済に比べればまだ可能性があるかと思います。私自身、金融機関との調整も含めて行うこともあるのですが、借換えを行う妻側の収入状況の他に離婚によって分与対象となる財産、継続的給付の内容等も含めて審査を行うようで状況によっては、借換え自体を行うことができなくないのではというのが私の感覚です。ただ、上手くいった上記の場合も、この方が正社員でかつ女性平均程度の収入があったこと、財産分与に基づく給付も相当程度の金額があったこと、養育費の金額も相応のものがあったこと等を考慮して、金融機関が判断したとのことでした。この方法自体も試してみる価値はありますが、なかなか厳しい理解して頂けますと幸いです。
他方で、借換えで行う際に、もう一つ試してみる方法として、保証人をつけることを確認するといったものです。ご両親やご兄弟がご協力して頂けるのであれば、この方法をとることで上手く進むことも少なくありません。ただ、この辺りの判断は金融機関によって異なることが多いので何とも言えないところです。
夫名義のまま妻が持ち家に住む場合
賃貸借契約を締結する方法
この方法自体を取ることはありえますが、その契約内容をしっかりと検討する必要があります。またその際に、例えば、養育費の支払い金額との調整で賃料(家賃)を調整してもらう等の考えはあり得ます。
ただ、この方法も賃貸借関係という賃借人がある程度保護を受ける態様ではありますが、相手方が所有権者であるので常にそのリスクを負うことになる点は注意が必要です。
使用貸借契約を締結する方法
使用貸借契約となるとあまり聞きなれないかもしれませんが、言うなれば賃料を払わずに居住するということになります。もっとも、これ自体、支払いがないので良いのは間違いないですが、そもそも相手方が合意してくれるか不透明であること、仮に合意してくれたとしても、賃貸借契約と比して、居住者保護に欠ける点が何点です。以上のようにメリットデメリットがありますので十分な注意が必要です。もっとも、この方法での解決が想定できるものとして、夫が不貞等の有責配偶者であり、妻側の合意がないと離婚ができない中で(いたるところで言われているように日本の裁判所は不貞行為に厳しく不貞行為を行った者からの離婚請求を相当長期間認めておりません)、その条件として、自宅の使用貸借契約を内容として出すことがあり得ます。この種の場合には、夫側がある程度収入もあり、社会的な信用もあることからローンの遅滞等も起こす可能性が低いのでこのような選択肢をとることもありうると思います。
一定期間の明け渡し猶予を求める方法
妻側としても、永続的に住み続けることまでは考えていない場合にこのような方法での解決を図ることが少なくないです。例えば、お子さんの年齢がある程度言っており、高校卒業までの間の明け渡し猶予を求めるといった内容で調整することは少なくありません。この種の調整を行うことになると、夫側も子どもへの負担はそれほどかけたくないということで、しっかり期限を区切り、退去するのであればと合意で調整することが少なくありません。
夫名義のまま妻が住み続けるトラブルリスク
自宅の売却は問題なく行えてしまう
まず対外的に権利者が夫側であるので、売買自体は夫の判断のみで行うことができます。財産分与未了の不動産の処理となるとやや難しい問題は生じ、買主との取引に効力を生じさせることまで検討するとより難しいということになります。そういう意味で、常にリスクを持ちながら居住するということになってしまいます。
ローンの支払い遅滞については、債権者による手続が可能になってしまう
支払い義務者である夫がローンの支払いができない、支払わないといった事態になることも少なくありません。そうなった場合、債権者は自宅から借り入れを回収することを考えます。
現に離婚後、そのような手続をなされてどうしたらよいのかといった相談を受けることも少なくないですが、なかなか打開策が少ないのが正直なところです。
以上のようなリスクを踏まえて、妻名義に変えることができればよいですが、これが難しかった場合、夫名義のまま住み続けるかを考慮することが必要です。
持ち家にこのまま住み続けたいですか。今後の生活を踏まえてしっかり検討することが必要です。
居住環境は自己のライフスタイルの根幹です
一般にどこで生活するかは、憲法上も重要な権利であるとか裁判例上も重要な権利であると言われております。ですので、ご自身の今後の生活において何にも換えて持ち家での生活を優先させたい場合は、これまで挙げさせて頂いたリスクを踏まえて持ち家での生活も考慮されて下さい。
もっとも、その上でも、以下で述べるようなリスクは加味して下さい。
自己の名義に変えることになると財産分与において金融資産の分与が減ってしまう可能性が高いこと
持ち家自体も財産分与の対象になりますので、その価値を算定すると一般的に高額になる可能性が高いです。住み慣れた家というのは、もちろん何にも代え難いですが、他の金融資産と比較して、自宅を取得することがご自身の今後の生活にとって良いかは支援して下さるみなさまと相談して決める必要があるかと思います。もっとも、この点は価値観の面も大きいので何が正解という点はありませんが、後悔のない選択ができるよう進められることを強くお勧めします。また、自宅の一部が相続で取得した不動産という場合はさらにこの点が顕著になります。
相手方名義のままであれば急な転居リスクは常に存在すること
先に述べたとおり、相手方名義である以上、常に転居リスクが存在することはやむを得ないところです。結局これをある程度やむを得ないリスクとして受け入れることができるのか否かというところをしっかりと検討されることを強くお勧めします。
よくある質問
何を基準に離婚後持ち家に住み続けるかを考えたらいいですか。
これは正解がありません。
結局ご自身次第と思いますと言ってしまうと何もならないのですが、私がお客様とお話する際には自己の権利にできるかを一つのポイントにしてはどうですかということが少なくないです。持ち家での居住を希望される多くの方は、安定した生活を今後もご自身やお子さんと続けていきたいと仰られる方が多いです。裏を返すと、安定した生活をできるか否かといった視点でみるといいのかなというのが私の経験上の考えです。どういうことかというと、これまで述べてきた通り、名義変更ができるか否かになるかと思います。ご自身の名義に変えてしまうと、今後の居住先について、自己でコントロールできますので、そういった意味で相手方名義の自宅に居住するのとは全く異なるかと思います。
自宅に住みたい以外に権利取得することに対するメリットはあるのか
これはあります。
私が対応した事件でもそれによって相応に依頼者様にとってメリットがありました。メリットの理由として、この件は、当初相手方である夫名義のままで自宅の整理を終える予定でした。もっとも、調停の進行に伴って不動産の評価についてお紛争が顕在化し、それなりの差額が生じました。端的に言うと、相手方提示の評価額であれば低すぎるがこちら側整理の評価額では高すぎるといったものです。そのような中で、私の方で検討したものとして、相手方評価額を前提に借換えがありうるかを当事の依頼者さんである妻に確認しました。実際に不動産業者さんともお話ししたところ、諸々の経費も差し引いても相応に利益が出るとのことでしたので、依頼者さんもその内容で良いとのことでした。相手方も全く問題がないとのことで、当方相手方に名義変更する内容が結局当方依頼者さんに名義変更する形の解決になりました。
このように、最終局面での調整ということは少なくありませんので、住みたい以外にも権利取得した方が良いことは少なくありません。また、この件は、実際に借換えを行うことができました。その際にも、ご本人の収入だけでなく、相手方より相応の財産分与、養育費を得られることができる前提で金融機関と調整することができました。
実際に妻が住み続ける場合、どのように進めることが多いか
ここまで見てきた通り、実際に妻が住み続ける場合で圧倒的に多いのは、ご両親による返済もしくはどなたかを保証人にすること等も入れた上での借換えなどです。妻側が住み続けるとなると結局これらのいずれかで解決することが圧倒的に多いですが、ごくまれに、養育費と調整する賃貸借契約や離婚条件との調整といった形で使用貸借にするといったこともあり得るといった状況です。
解決事例
ご依頼前
本件は、先ほどのよくある質問でも挙げた事案ですが、介入前について夫側で自宅を取得する整理で双方それほど争いなく進んでおりました。
ご依頼後
介入後、実際に協議の様子を見ていると争いのないように見えていたのは、協議が進んでいなかっただけということが発覚し、どう進めていくべきか思案したのを今でも覚えております。
ここから先は、よくある質問の回答でも書いているととおりですが、双方の共通の利益を探し出して、そうなると当方依頼者が取得する方がよいと考えてそこからは、金融機関と調整して、無事借換えすることができました。
実際の解決
上記流れでの解決になるのですが、記事中にあったとおり、自宅を取得することで財産的給付の金額自体は減少することになりました。もっとも、この不動産自体も売却することになったので、調停手続で相手方が取得するより結局依頼者さんが取得して、売却した方がメリットのある結果になりました。
解決後、依頼者さんからは想定していなかった方向でビックリしていますが、自分にとってメリットのある解決なので、良かったです。とおっしゃられていたのが印象に残っております。
まとめ
大切なのは「現実的な選択と早めの相談」
離婚後も自宅に住み続けたいという思いは、ごく自然な感情です。ただし、それを実現するためには、法的な手続き・契約内容の整備・資金計画の確保が不可欠です。
特に次の点及びそれにかかる費用を早期に確認・相談することをおすすめします:
・不動産の名義状況
・住宅ローンの残高
・自分に名義変更が可能か
・金融機関との借換え調整の可能性
離婚は人生の大きな転機です。今後の生活を安定させるためにも、不動産については「感情」ではなく「冷静な判断」と「計画」がカギになります。
弁護士への早期相談の利用が、後悔のない選択への第一歩です。
あなたに合った選択肢を一緒に考えてみませんか?
「このまま家に住みたいけど、どう進めればいいか分からない」
「名義変更って簡単にできるの?」
「借換えってどうやってするの?」
そんなお悩みがあれば、ぜひ専門家に相談してみてください。情報を整理し、あなたにとってベストな方法を一緒に見つけていきましょう。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
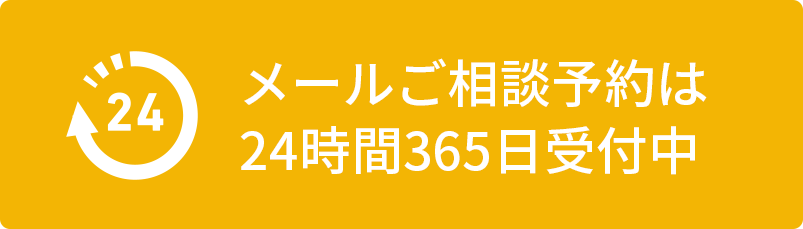

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。