【弁護士が解説】特有財産とは?財産分与に影響する重要ポイントと注意点
離婚目次
はじめに
当事務所では、離婚や財産分与に関するご相談を多く取り扱っております。
離婚の際、よく問題になるのが「財産分与」。
その中でも特に注意したいのが、「特有財産」という考え方です。
今回はこの「特有財産」とは何か、どうやって見分けるのか、共有財産との違い、立証方法、そして実際に解決した事例まで、詳しく解説していきます。
特有財産とは
定義(民法762条1項)
特有財産とは、婚姻中であっても夫婦の一方のみに帰属する財産。
⇒財産分与の対象にはならない。
典型的な特有財産の例
・婚姻前から保有していた財産(預貯金、不動産等)
・相続によって得た財産
・両親からの贈与財産
・障害年金や慰謝料(内容次第)
共有財産との違い
共有財産とは?
夫婦が婚姻後に協力して形成した財産。
⇒ 財産分与対象になる。
判断基準
婚姻後に形成されたかどうか
夫婦の協力があったかどうか
特有財産としての立証ができない場合、共有財産とみなされる
特有財産の考慮方法
基本的な考え方
総財産 - 特有財産 = 共有財産(分与対象)
定義のとおり、全体財産から特有財産を控除するという形で計算することになります。
具体的には、500万円の財産のうち、200万円が特有財産とするとこの金額を控除すると、300万円が夫婦共有財産になるということになります。
自宅ローンについて
自宅ローンについて、上記特有財産の考えに照らして考えると、特有財産の割合で調整すると思われますが、少し複雑の考えをするのが現在の家裁実務慣行です。大きな考え方として、特有財産部分の金額の算定において、残ローン部分を考慮しないことが現在の家裁実務の大勢になっております。かなり複雑ですが、特有財産の支出は相応に考慮されることになるので、しっかりとその点を調査することが必要です。専門的な部分になってしまいますので、該当される方はご相談の際に確認されて下さい。特に、残ローンがあり住宅購入費用部分に特有財産も存在する際に注意を要します。
特有財産の立証方法
特有財産の立証は、財産の形成過程・維持過程が夫婦協力の下でなされたと言えるものでないと評価されることが必要になっており、なかなかハードルが高いのが現状です。以下の問題となることが多いケースでご説明しますが、相手方が特段争いことなく、前提になっているのであれば問題ありませんが、そうでない場合は、客観的資料も踏まえて、立証をすることが重要になってきます。
特有財産の問題となることが多いケースと立証方法
不動産の一部資金のご両親からの贈与について
事実関係について、共通認識であることも少なくないので争われないことも少なくありません。
金額等が争いになった場合は、不動産ローンの契約書からローン金額以外が贈与であるといったことや直前のご両親の引出履歴をもって証明することなどが少なくありません。前述のとおり、持ち家購入の際のローンの一部の贈与になると、相応の金額になることも少なくないので、しっかりと主張することが重要になってくるかと思います。
預貯金について
預貯金について、特有財産と立証することが難しい面もあります。言うなれば、夫婦共有財産混在しているとして(特に、婚姻前から同じ預貯金通帳を使っている場合は明確に区別するというところが難しいところです)、立証が事実上困難であるという点もあり得ます。
通帳を明確に分けている場合はそれを示すという方法がありますが、他方でそのまま使っている場合は、婚姻前の財産が維持されているということを主張して、立証できるよう取引履歴もしくは通帳の履歴を示していく必要があります。
その他、例えば障害年金やご両親からの援助についても、共有財産の中に特有財産が残存していることをしっかりと主張することが重要になってきます。
その他、よく紛争になるものとしては、子ども名義の預貯金ということになります。これは原資次第になりますが、終局的な贈与(お年玉等がその代表例です)であれば子ども自身の財産であり、お子さんの財産になりますが、他方夫婦のお金を溜めていた場合等は、共有財産として扱われます。
婚姻期間前の生命保険の解約返戻金及び退職金について
これらについて、財産分与の対象であることは現在の実務に則してほとんど争いがありません。過去、退職金が財産分与対象財産になるのか議論がありましたが、現在の実務では、給与の一部が後から給付を受けるものであることを前提に給与であれば夫婦の協力の結果であり、財産分与の対象であることにほとんど争いがありません。
これらの財産の財産分与対象外の特有財産部分の算定については、共有財産に該当する部分を割り戻す計算をする形で財産分与対象財産の計算をすることになります。どういうことかというと、就労期間が300か月あり、その中での婚姻期間が150か月であるとすれば、退職金と算定した金額の2分の1が財産分与対象になるので、上記就労期間及び婚姻期間が分かる資料が必要になるということになります。就労期間もしくは保険加入月数は算定資料に記載があり、婚姻期間は戸籍を確認することで判明します。
| ケース | 証明に使える資料 |
|---|---|
| 親からの贈与 | 銀行送金記録、贈与契約書 |
| 婚前の預貯金 | 通帳の履歴、入出金記録 |
| 相続財産 | 遺産分割協議書、振込記録 |
| 退職金や保険の解約金 | 就労期間と婚姻期間の証明書類 |
確実に特有財産の認定を裁判所から受ける方法
特に預貯金として混ざってしまうとかなり困難です。
ここまで見てきたとおり、不動産ローンや保険の解約返戻金、退職金についてはある程度算定資料や手続の中で用いる資料で一義的に明らかになるかと思います。他方でネックになるのが、預貯金として混ざってしまう可能性のあるものです。
夫婦の協力の結果得られたものでないのですから、ご両親の遺産や贈与、婚姻前の預貯金、損害賠償金(これについては費目によって異なります)は、当然財産分与の対象ではありません。もっとも、特有財産であるということを示すのは、そのことを主張するものが行う必要があるのであり、これが立証できない限り夫婦共有財産とみなされてしまいます。
裁判手続きの難しいところは、神様の視点で物事を見ることができるわけではなく(絶対的な真実を裁判所が把握できるわけではないという趣旨です)、資料として出されたものから合理的なものの判断を行う手続きに過ぎないということです。そうなると、共有財産と特有財産が混ざってしまいどの部分が特有財産かの判断ができないということになると、結局全て共有財産という判断になりかねません。制度上ある程度やむを得ないですが、真実のとおりの判断を受けるためには十分な準備を行うことが必要です。
預貯金として、混ぜてしまわないことが何より大事です。
究極的に、しっかりと特有財産を整理するのであれば特有財産を個別に管理することが必要です。どういうことかというと、特有財産と夫婦共有財産を同じ口座で金銭管理しないことが重要であるということです。具体的に言うと、婚姻前の預貯金と婚姻後の口座を分けるであったり、遺産・贈与・損害賠償金を受け取ったのであればそれ用の口座の作成をしておくということになります。かなり手間ですが、こうすることで、神様の視点では特有財産であるが、裁判手続きの兼ね合いで共有財産とみざるを得ないという可能性を除外することができます。
もっとも、円満な婚姻関係の際にこのような状況を想定して、財産を明確に整理していることはそれほど多くないと思います。離婚することになった際にやることをやっていくというのが現実的でありますので、一緒に対応を考えていければと思います。
よくある質問
特有財産の立証で成功することはありますか
もちろんあります。
比較的容易な生命保険や退職金はほとんどの事例で成功しております。
他方で、これまで預貯金自体が本人名義であるがご両親名義で掛けていたことを立証に成功し、裁判所にその内容を前提とする和解の提案があった事案もございます。他には、慰謝料について、特有財産であることを前提に調停合意した事案もございます。立証が難しいのは間違いないですが、あきらめず主張することで裁判所がこちらの主張を受け入れてくれることもあります。
特有財産の主張で特に意識した方が良いことはありますか。
こちらの主張が証拠で全部支えられることは性質上厳しいので、部分部分で証拠が存在することをしっかりと主張すべきです。
特有財産の主張以外の場合でも現実的に、主張の全てが証拠で裏付けられていることはなかなかありません。そうであれば立証できていない、裁判所が認定してくれないとするとほぼすべての事実の認定が取れなくなってしまいます。多くの事件では、主張に沿った証拠を示すことで、この証拠があるのであればこちらの主張(もっと言うと事実関係で「ストーリー」といったりします)が合理的であると裁判所に思ってもらえるかです。その為に、現実的にある証拠を用いていくべきで証拠全体があるという考えでなく、今あるものでどういうストーリーで構成できるか、といった視点で考えることが大事です。
特有財産の主張で争いがある場合、裁判所が当事者の話を聞くことはありますか。
もちろん存在します。
裁判手続きであれば尋問、審判手続きであれば審問という手続きで行います。
行われることが多いのは、弁護士による書面の整理だけでなく、ある程度本人から話を聞いた上で、事実関係の整理をしたいという際です。私が対応した事案でも審判の際に妻による夫特有財産の管理使用状況について、詳細に確認されました。この事案について、原審では審問内容はあまり考慮されなかったのですが、抗告審(家事審判における第二審です)で相応考慮して頂けました。なお、遠方であれば近くの裁判所を利用して、電話等で行うことも少なくありません。
特有財産対策として、口座を完全に分ける以外の方法は何かありますか
現状ありうるのは、婚前契約です。もっとも、法改正がなされており施行時期は未定ですが、婚姻後の財産関係を規律する婚後契約を利用するといった方法が考えられます。
婚前契約は、婚姻前に何を特有財産に整理するといったことを定めるものです。形式等の定めも十分ありますので、確認する必要があります。また、婚後契約について、これまでいつでも取り消しうるとされておりましたが、改正法の施行によって規律が変わりますので、十分注意が必要です。
財産分与の協議を通して、特に考慮されるべきことは何ですか
基本的には、基準時時点の財産を双方で整理し合った上で、特有財産を除外する計算をして取得財産についての考えを整理して進めることになります。これが前提ですので、基本的には収入状況や養育費の金額等はあまり影響しません。
解決事例
受任前
夫側で依頼を受けることになりましたが、妻に財産管理を任せていたところ、自分の特有財産である遺産がかなり引き出されており、どこにもないといった状況でした。
その上で、ご自身自体、公務員でしたので、相当の財産分与を請求されていたので、どうすべきかといったことをかなり悩まれている状況でした。
そこで、ある程度履歴から一緒に捜索をした上で進めていきしょうということで、ご依頼頂きました。
ご依頼後
まず、お話頂いていた遺産の払戻資料から、時期的な特定を行い、その上で、財産分与調停・審判を通して、管理を妻がしていたことを前提に、引出について確認を行いました。結局金融資産に一部なっており、その部分について財産分与に汲み込むことができました。
その上で、遺産が入った預貯金自体は、共有財産と特有財産が混ざってしまっているとされました。ところが、原審もそれでは決定として座りが悪いと考えたのか分かりませんが、現存している遺産が一度入った預貯金のみ寄与割合を変動させるといった結論を出しました。
解決に向けて
もっとも、私と依頼者さんは、相手方が従前審問期日や書面の中で遺産から金融資産を購入したことを認めておりましたので、その事実を前提にしないのは不当であると述べて、高等裁判所に即時抗告しました。
そうしたところ、同部分に関する主張を高等裁判所が受け容れてくれて判断の変更がありました。
その部分の変更を、私と依頼者さんは嬉しかったのですが、結局遺産の大部分は消えてしまっていたので、裁判手続きには勝ったが事実上金銭の返済はされないというジレンマでした。
私の中では今でも忘れられない事件でした、決定自体は喜ばしいものでしたが、何とも歯がゆいものでした。
まとめ
特有財産の主張はしっかりとすべきです
これまで述べてきたとおり、特有財産の立証はなかなかハードルが高いです。それも、共有財産と混ざってしまうと、どう進めるか困難を極めます。もっとも、夫婦で協力したわけでもないのに、それを分与の対象にするのは納得できないと思いおますので、悔いのないようにやれることはやるべきというのが私の考えです。
今あるものでやれることをやりましょう、気軽にご相談ください
ご相談頂ければ現状で何ができるかを私の経験なりにお伝えさせて頂けます、その上で、どう進めたいかをご自身で悩んで考えて頂き、ご納得頂いた上で一緒に進めていきたいと考えております。ご自身の事ですので納得できない形で終了してしまうと後悔しきれないと思います。
現状でできることをありのままお伝えさせて頂きますので、お悩みならお気軽にご相談ください。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
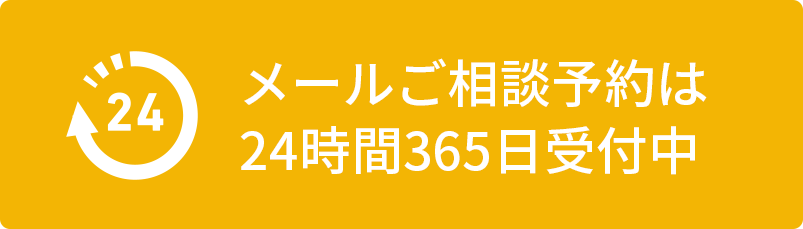

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。