親権争いで母親が有利なのは本当?家庭裁判所の判断基準を弁護士が解説
離婚目次
はじめに
現在、民法改正により「共同親権制度」が導入され、2026年に施行予定です。今後は親権紛争の構造自体が変化する可能性がありますが、本記事では、現時点での家庭裁判所の判断基準に基づいた内容を解説しています。
要点整理:この記事でお伝えしたいこと
「母親有利」は一部真実、だが絶対ではない
家庭裁判所は「母親だから有利」ではなく、「主たる監護者か否か」「監護状況に問題がないか」を重視。
実際には母親が出産・育児の中心を担うケースが多く、それが有利に働く傾向にある。
裁判所が親権・監護権を判断する基準
以下のような観点が総合的に評価されます。
主たる監護者は誰か
現在の監護状況に問題がないか
子どもの意思(10歳以上で重視)
きょうだい不分離の原則
母性優先(ただし性別ではなく育児能力)
面会交流への協力性
監護補助者の有無
父親が有利に進めるには
離別前から育児に積極的に関与している証拠を残すこと。
別居時に子を連れて行かれたら、即座に家庭裁判所での手続きを行うべき。
「監護の継続性」が重要視されるため、初動が非常に重要。
審理の流れ
監護者指定審判・保全処分申立て
家庭裁判所調査官による調査
裁判所の審判
即時抗告(高裁)
判決後の子どもの引渡し(任意or強制執行)
離婚調停や財産分与等の話し合い
現在の日本の社会構造上母親有利です
現状の裁判所の基本的な判断構造
主たる考慮要素
従前の主たる監護者による監護状況に問題がなく、その者による監護が継続している場合は、よほどのことが無い限り監護を継続させることが子の生活に資するとする判断傾向が強いです。理由としてよく言われているのは、監護能力にたけている者が監護継続することが子の養育に資しており、発育環境として望ましいためとされております。
その他の考慮要素
子の意思の尊重
この要件自体は、子の年齢に依存するかなというのが正直なところです。例えば、10歳を超えると、この要件がかなり重視されますし、他方でそれ以下であれば現状の監護親からの影響を相当受けうるとしてそれほど考慮されません。
きょうだい不分離の原則
これもどの程度見るか現状の家裁実務に照らすと何とも言えないかなというのが正直なところです。過去に私が担当した案件でも、監護が継続している状況の長女と乳児段階の長男という姉弟でしたが、従前の監護状況及び現状の監護を踏まえて一人ずつといった判断になりましたので、それほど重きを置いた要素なのかもしれないというのが現状の私の印象です。もっとも、担当の裁判体によって判断が変わるというのはこの種の事案では特に多い印象です。
母性優先の原則
これは、「母親」が重要という訳ではなく、綿密かつ充実した監護をいずれができるかというものです。もちろん父親ができれば問題ないですが、一般的には母親の方がより綿密に監護できるとされており、特に乳幼児であればこの点がより考慮されるイメージです。もっとも、この要件で判断がかなり影響を受けるということはそれほど多くないのが正直なところです。
面会交流への許容性
この要件は、意外と判断に影響を及ぼすことは少なくありません。過去の私の事案で別居後、子にある種の影響を与え、面会交流に際して、敢えて他の予定を入れ早期に面会を終わらせるよう進めたといった事案では(ここまでの事実認定を取得するのが相当苦労しました)、その事実も加味して、面会交流に非協力的であることを非難した上で、判断がなされました。
監護補助者の存在
これについては、十分な監護補助者がいないと監護が立ちいかなくなるという場合に考慮される事項であると主に考えて頂ければと思います。
裁判所の判断構造をみると母親が有利になります
現在の日本の社会構造上、母親が出産後しばらく産休・育休を取ることが少なくないように思います。その前提からすれば、監護を主として担うのが母親になる以上、上記判断基準に照らすと母親が有利になる可能性が高いです。そして、多くの場合、これ自体の良し悪しは別にして、婚姻関係が悪化すると、母親が子と共に別居することが少なくなく、そうなると母親が子をめぐる紛争に有利ということになってしまいます。
判断要素のまとめ
| 判断要素 | 裁判所の重視度 | 備考 |
|---|---|---|
| 主たる監護者 | ◎(最重要) | 現在・過去の育児の中心人物かどうか |
| 監護状況の安定性 | ◎ | 子の生活環境が安定しているか |
| 子どもの意思 | ◯(年齢による) | 10歳以上で重視される傾向 |
| 母性優先の原則 | △ | 性別よりも育児能力重視 |
| 面会交流への協力度 | ◯ | 非協力的な場合マイナス評価あり |
| きょうだいの分離回避 | △ | 必ずしも重視されない場合もあり |
| 監護補助者の有無 | △ | ワンオペ育児に無理がないか確認される |
母親が有利といえない場合
前提
日本の裁判所は、母親が監護する方が子にとって幸福であるという考えを持っているわけではありません。主たる監護者がいずれであったか、現状の監護に問題があるかの点を見ているに過ぎませんので、その点に注意が必要です。ですので、以下のような場合には、母親が負ける可能性があります。
主たる監護者でなかった場合
職種や収入状況によれば、妻が主として働き夫が家事・育児の主体となることも少なくありません。そうなると、主たる監護者は父親である夫ですので、この理論が当てはまりませんので、母親有利とはなりません。
従前の監護状況が不適当であった場合
上記判断基準に照らすと、従前の監護状況に問題がなかったからこそ、その経験を活かしやすいというものです。裏を返せば、監護状況に問題があったのであれば、その経験を活かしても子にとってメリットにはなりません。何をもって、裁判所が子にとって不適当と判断するかは、裁判体にとって区々というのが正直なところですが、私の経験上は、不貞行為(不倫)をもって不適当とする裁判官もいれば、これだけでは不適当と判断しない裁判官、精神的な不安定さをもって不適当とする裁判官といったようにかなり判断が分かれる状況です。その他、虐待と評価されるような育児放棄・ネグレクト等も監護者としての適格性を欠くと言われております。
現状の監護が他方配偶者である夫である場合
ここも裁判官によってかなり分かれるところですが、別居の態様に着目することが多いというのが私の印象です。特に、従前の主たる監護者とは別の者が監護するに至っている場合については、監護に至った経緯に着目している状況です。そうなると、別居開始の態様によって、現状の監護状況が重要になってくると言えるかと思います。
親権者・監護権における具体的審理の流れ
家庭裁判所への監護者指定及び引き渡し請求の審判及び保全処分の申立て
現状の家裁の運用において、監護の継続性も重要な考慮要素になっている状況では、一刻も早く申立を行う必要があります。書面の記載についてもやや独特のものがありますので、連れ去られてしまったら、早急に弁護士事務所にご相談の上、この種の事案に慣れている事務所に対応を依頼すべきです。なお、本審判については、早期に対応を求めることが必要ですので、同時に保全処分を求めることが必要になります。なお、この種の事案で「協議」を行ってもなかなか話が進むことはないので法的手続きを進めることが多いです。
具体的審理
多くの場合、申立書に対する反論と並行して、状況を踏まえてということになりますが、子の監護状況の調査を家庭裁判所調査官が行うことになります。ここでどのような調査を行い、誰に調査を行うかは審判官(裁判官)によって判断が分かれるところですので、調査を求めたい部分については十分主張をすることが必要です。ここで行われる調査官の調査において、「調査官の意見」が出されることが少なくありません、というより多くの事案で出されます。その判断がほぼ原審の判断になってくると考えて頂いて問題ございません。裏を返せば、この調査報告書を準備している段階でどのような資料を提出できるか、準備をできるかということになってきます。そこを意識しながらの期日進行が重要になってきます。原審の判断においては、この結論部分は相当重要視されますが、高等裁判所での即時抗告審においては、結論というより顕出されている事実を拾っているイメージです。ですので、結論も重要ですが、原審の判断がどうなるか分からない面もありますので、顕出させたい事実を出して、調査の土俵に挙げておくことが何より重要であると私自身は考えております。
審判官(裁判官)による調整
多くの事案で、判断前に審判官による調整がなされます。より具体的に述べると、不利な判断になる方に一定程度の面会交流の話合いを行うことで調整ができないかということを持ちかけることです。審判という判断をすると、即時抗告(高等裁判所への異議申立てです)が行われる可能性が高く、そうなると、紛争の長期化に繋がり当事者及びお子さんにとって良くない結果になりかねません。また、早期のより充実した面会交流の為にこのような形が取られることが多いです。ここでは実際の高等裁判所での見通しと具体的交流の内容を踏まえて調整をすることが必要になってきます。
決定
上記の調整が上手くいけば柔軟な解決を行うことができますが、調整が功を奏さなかった場合、裁判所による判断がなされます。これは、白か黒かではっきりした決定が出てしまい、文字通り、勝ち負けが明確に出ることになります。その後、原審の判断の理由を踏まえて、補完できるところがあれば補完した上で、即時抗告を行うことになっていきます。
即時抗告審(第二審の判断)
形式的には、最高裁での判断もありますが、相当ハードルが高く、事実上最後の審理を受ける機会ということになります。多くの場合、抗告する方から申立及びその理由書を提出し、必要に応じて相手方が反論するという審理になっております。法律上、再度の調査等は可能ということになっておりますが、事実上書面の判断で結果が出ることがほとんどですので、提出書面の内容が重要ということになってきます。
判断後任意の引き渡しもしくは強制執行
判断後任意の引き渡しを受けることができればいいのですが、任意に引き渡しがされないということも少なくありません。そうなると強制執行手続きを行う必要があるのですが、そう簡単ではありません。どう進めるのが良いのかという点について方法は種々ありますので、十分に検討されるべきです。相手方の不履行に対して金銭給付で威嚇する間接強制、引き渡しを直接的に実現させつ直接強制等種々の方法がありますので、十分な検討をなされるべきです。昨今、直接強制の方法についても法改正で変更されている部分が多いので、何が一番有用であるかなどしっかり検討されることを強くお勧めします。
その後の手続
お子様に関する紛争が終わっても、夫婦間の問題は残っているかと思います。その後、離婚等の手続を進めていく必要がございます。
何をどう進めるかをご自身の中でしっかりと把握して進められることをお勧めします。
実際に子供に関する親権紛争が終わった後も離婚調停の中で養育費・財産分与・浮気に対する慰謝料といった点で協議が行われることがほとんどです。
父親が有利に進める方法はあるのか?
この点については、正直なかなか難しい点が否めません。
その上でですが、まず、前提としてお子さんと離れないようにすることに加えてご自身の監護実績を残す事、ここからは状況に応じてですが、母親が連れて行かないことに対する合意を取っておく等が方法としてはあり得ます(ただ、その話合いをすると相手方が何かを察知する可能性が高いです)。その他、例えば以下のような方法が考えられます。
・母親の不在時に子を預かっていた日誌・写真を残しておく
・保育園・学校行事への参加記録を保管
・LINE等での育児に関する会話履歴の保全
親権者・監護権者争いに対する弁護士の思い
昨今、実子誘拐であるなど述べられ、この辺りの議論がかなり活発になっているかと思います。私自身この部分は、双方の言い分があるので何とも言えない面があるのは間違いありません。もっとも、現状の裁判所の判断があるにせよ、お子さんの事を第一に考えて動いて行かれるべきではと個人的には思っております。お子様が健全に成長発育するためには、相手方と断絶するより、十分な交流する等色々と検討して進まれる方が、広い意味でご自身にとっても良い結果に繋がると思います。
よくある質問
子どもを妻に連れて出ていかれたのですが、どうしたらいいですか
今後お子さんと生活することを考えているのであれば、早急に家庭裁判所での手続きを進めるべきです。
可及的速やかに複数の事務所へご相談の上、ご対応を依頼されることを強くお勧めします。
監護者手続においてどのような弁護士を選ぶべきですか。
これまで対応経験のある弁護士の方を検討された方が良いと思いますが、必ずしもそこにこだわるというよりは、熱意をもって動いてくれる弁護士の方が良いかと思います。ご自身がこの弁護士という弁護士さんを選んでください。なお、この種の手続自体、ある程度弁護士の初動で動く必要があるので、費用面もしっかり確認されることをお勧めします。
自分で監護者手続は可能ですか
端的に言ってご自身で進めるのは難しいと思います。私の感覚では調停についてはできなくはないが(それでも簡単ではないです)、審判は難しいと考えております。
申立が遠方の裁判所の場合、どのように手続きが進みますか
現在、多くの場合電話・ビデオ会議のリモートで手続きを行っております。ですので、リモートであるから不利に扱われるということもありませんし、交通費の負担ということもそれほどありません。
解決事例(不仲を原因に離婚協議中、子どもを連れていかれ紛争になったケース)
受任前
この方がご相談に来られた際は、お子さんを連れていかれた直後で途方に暮れられていたことを今でも覚えております。お子さんを連れていかれた直後で、相手方に弁護士を就けられ、直接の連絡すらできないようにされるといったん状況でした。もっとも、この件は母親側の事案でした。なお、受任前に離婚についての協議は進んでいたようですが、お子さんに対する教育への価値観の相違等を原因として問題になっていたようです。
受任後
受任すると同時に管轄裁判所に監護者指定審判及びその保全処分の申立てを行いました。
そして、審理が進んでいったのですが、その中での調査官による調査報告では、従前の主たる監護者が当方依頼人でありかつその監護状況に問題ないこととしつつ現状の監護に問題ないので、相手方である父親を監護者とすべきといったものでした。この件について、別居開始の態様がいわゆる連れ去りと評価しうるものであったこと、別居後の生活についても父親側があまり監護できておらず、事実上子どもにとって祖父母が主として看ていたという事案でしたが、その点もあまり原審の裁判所は考慮しておりませんでした。
そうした事情もあり、いわゆる実務慣行とも必ずしも一致しないといった結論になり、依頼者さんと相談し、即時抗告審に挑みました、
解決に向けて
その結果、こちらの主張が身を結び、別居態様であったり、これまでの監護状況であったりをしっかりと評価され、その上で、母親側が監護者であるという判断になりました。
上述のように、調査報告で上がってきた事実自体は、引用した上で結論部分について高等裁判所の3人の裁判官がしっかり検討してくれた結果本結論になりました(高等裁判所は、3人の裁判官での判断になります)。
この判断が届いた際、依頼者様にご報告した際の喜びの声は今でも忘れません。ただ、改めてこの種の審理において、裁判官によって判断が変わるものであると実感したものでもありました。
まとめ
親権や監護権が女性有利というのは間違いではありませんが、現在の判断基準を前提にするものに過ぎません
親権や監護権について、「母親だから有利」というのはあくまで社会的背景や育児の実情を踏まえた結果論に過ぎず、裁判所は性別ではなく“子の福祉”を最優先に判断しています。
だからこそ、
- 育児への積極的な関与
- 初動の速さ(連れ去り直後の対応)
- 証拠の準備
が、どちらの親にとっても最も重要です。
お子様の為にもしっかりとした準備が必要です
父親がでも母親側でもやれることはやるべきですし、これをしないと後悔ばかり残ってしまうかと思います。現状の裁判所の判断枠組みのなかで何ができるかを考えて、しっかりとした対処の為にこの紛争が生じてしまった際はできるだけ早期に法律事務所へご相談の上、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)
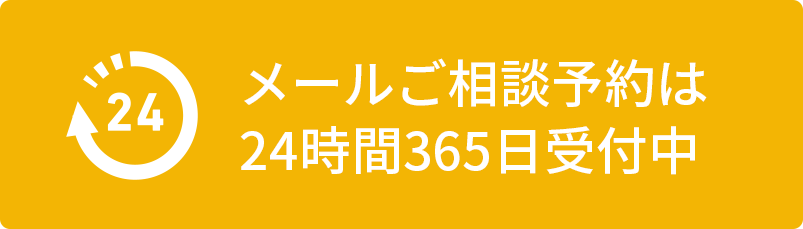

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。